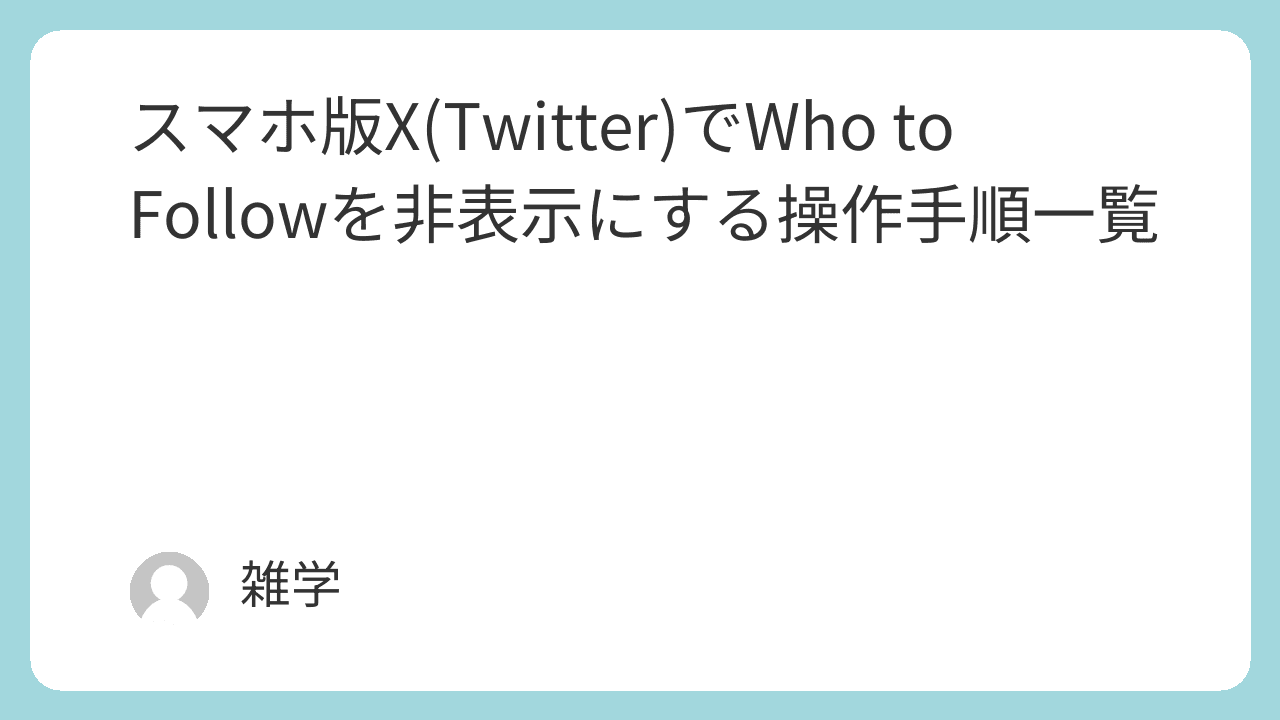X(旧Twitter)をスマートフォンで使っていると、画面にたびたび表示される「Who to Follow(おすすめユーザー)」が気になることがあります。
興味のないアカウントが並ぶと、画面が見づらくなるだけでなく、誤ってフォローしてしまう可能性も。
この記事では、スマホ版X(旧Twitter)で「Who to Follow」を非表示にするための具体的な手順や、表示を防ぐための対策を詳しく紹介します。
Who to Followをスマホで非表示にする方法

iPhoneとAndroidでの設定手順
iPhoneとAndroidのどちらの端末でも、X(旧Twitter)アプリの設定メニューから「Who to Follow」の表示を減らすための調整が可能です。
まずは、X(旧Twitter)アプリを起動し、左上にある自分のプロフィールアイコンをタップします。
メニューが表示されたら、「設定とプライバシー」を選びます。
続いて「通知」セクションを開き、「プッシュ通知」をタップしてください。
その中にある「おすすめアカウント」の項目を見つけて、スイッチをオフにすることで、X(旧Twitter)からのおすすめユーザー通知が届かなくなります。
この設定により、通知欄に表示される推奨アカウントが減少し、表示の煩わしさを軽減することが期待できます。
また、一部の端末やアプリのバージョンによっては、設定項目の名称や配置が異なる場合があります。
たとえば、「通知」ではなく「コンテンツ設定」や「表示設定」といったメニューに項目が含まれていることもあるため、設定画面内の用語に注意しながら探すことが大切です。
「おすすめ」「関連アカウント」「興味・関心に基づく通知」などの表現が見つかった場合、それが対象の設定である可能性が高いです。
少し手間はかかりますが、これらの設定を丁寧に見直すことで、より快適な利用環境が整えられます。
非表示にしても表示される場合の対処法

おすすめタブや通知欄に出てくるケース
アプリ内の「おすすめ」タブや通知欄では、たとえ設定を変更したとしても、しばらくの間は「Who to Follow」が表示されることがあります。
これはX(旧Twitter)側のアルゴリズムや一部の通知仕様が即時反映されないためで、完全な非表示設定が反映されるまで時間がかかるケースもあります。
こうした場合には、該当タブをできるだけ使用せず、別のタブ(例:「ホーム」や「リスト」)をメインに利用することで、視界に入る機会を減らすという方法もあります。
さらに、通知そのもののカスタマイズを行うことで、不要な提案通知の表示頻度を抑えることができます。
通知設定内の「おすすめユーザー」や「X(旧Twitter)の提案」などの文言がある場合は、それらをオフに切り替えておきましょう。
非表示設定が反映されないときの確認点
設定を変更しても「Who to Follow」の表示が残っている場合、まず最初に反映までのタイムラグを考慮する必要があります。
通常は数分〜数十分で反映されますが、環境によっては数時間かかることもあるため、焦らずに様子を見ることが大切です。
また、一度X(旧Twitter)アプリを完全に終了してから再起動する、あるいはログアウトしてから再ログインするなどの基本的な操作も有効です。
それでも改善されない場合は、アプリのキャッシュを削除するか、アプリ自体を最新版に更新することで、正常に反映される可能性が高まります。
どうしても表示が消えない場合は、X(旧Twitter)の公式サポートに問い合わせることも選択肢の一つです。
Who to Followを完全に消すための追加対策
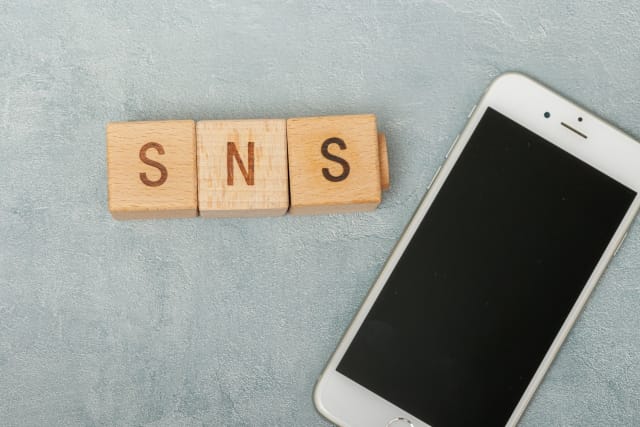
X(旧Twitter)の興味・関心の設定を見直す方法
X(旧Twitter)の「興味関心」データは、「Who to Follow(おすすめユーザー)」の表示に大きく影響します。
そのため、アカウントに紐づけられている興味・関心の情報を見直すことで、表示されるユーザーの種類や頻度を制御することが可能になります。
以下の手順で設定内容を確認・変更してみましょう。
- X(旧Twitter)アプリまたはブラウザから「設定とプライバシー」を開く
- 「プライバシーと安全」セクションを選択
- その中の「広告の設定」へ進む
- 「興味関心」という項目にアクセスし、自分に不要だと感じるジャンルや項目のチェックを外す
-
興味リストは複数あるため、スクロールして全体を見渡しながら見直すのが効果的です
不要な項目を外すことで、関連するアカウントが推奨される確率が減るため、「Who to Follow」の精度や内容を調整することができます。
特に、過去の閲覧履歴やフォロー傾向から自動的に追加されている項目もあるため、定期的な見直しが推奨されます。
非公開アカウントに切り替えるメリット
X(旧Twitter)アカウントを非公開設定にすることで、他のユーザーやアルゴリズムからの注目度が下がります。
非公開アカウントにすると、フォローリクエスト制となり、見知らぬユーザーとの接触機会が制限されるため、X(旧Twitter)が「この人におすすめしたい」と判断する機会も減少します。
その結果、「Who to Follow」の提案頻度が低くなる可能性があり、タイムラインがすっきりとした印象になります。
また、非公開設定によって自身の投稿やフォロー関係が一般ユーザーに見られにくくなるため、プライバシー面でも安心感が高まります。
ただし、非公開にすることで得られる利便性と引き換えに、新しいフォロワーの獲得機会が減る点にも留意しましょう。
誰かにバレる?非表示設定の影響と注意点
相手に通知される心配はあるのか?
「Who to Follow」の非表示設定をしても、X(旧Twitter)から特定の相手に通知が送られることは一切ありません。
たとえば、「この人を表示しない」や「おすすめをオフにする」といった操作は、あくまでも自分のアカウント内での表示設定に過ぎず、他のユーザーのタイムラインや通知には一切影響を与えません。
誰をフォローしているか、誰の表示を控えるかといった行動が他人に知られることはないため、安心して表示のカスタマイズを行うことができます。
また、設定を変更しても過去の行動履歴などから一時的に表示される可能性はありますが、それが相手に伝わることはありません。
推奨ユーザー表示の挙動とその仕組み
X(旧Twitter)で表示される推奨ユーザーは、複数の要素をもとにアルゴリズムが自動的に選出しています。
主な要素としては、自分がフォローしているユーザーのつながり、いいねやリツイートの履歴、検索履歴、興味・関心として設定されたカテゴリ、さらには最近よく閲覧しているプロフィールなどが含まれます。
このような情報を総合的に判断して、「このアカウントが気に入りそう」と判断されたアカウントが推奨される仕組みです。
そのため、完全に表示をゼロにすることは難しいのが現状です。
ただし、表示頻度や内容を調整することは可能です。
興味関心の設定見直しや、通知のカスタマイズ、非公開アカウントへの切り替えなどの方法を組み合わせることで、表示を抑えることができます。
特に、アルゴリズムはユーザーの行動に応じて学習していくため、表示されたくないジャンルのアカウントを見ない・関わらない姿勢を続けることで、徐々に推薦内容も変化していきます。
長期的な視点で調整を重ねることが重要です。
Who to Followが表示される理由とは
興味関心・フォロー関係による推薦ロジック
X(旧Twitter)では、利用者がフォローしているアカウントや、頻繁に閲覧している投稿内容に基づいて、「Who to Follow(おすすめユーザー)」が表示されます。
たとえば、自分がフォローしている人の多くが同じアカウントをフォローしている場合、そのアカウントが推薦される可能性が高くなります。
また、特定のジャンルや話題に関するツイートをよく閲覧していると、類似したジャンルのユーザーが「おすすめ」に表示されやすくなります。
このように、X(旧Twitter)のアルゴリズムは、ユーザーの興味関心やフォロー傾向をもとに、自動的に関心の高そうなアカウントを抽出し、提案する仕組みをとっています。
さらに、過去のいいね履歴や検索したキーワード、最近チェックしたプロフィールなどの行動もアルゴリズムの判断材料となっています。
一度でも何かしらのアクションを起こしたジャンルは、今後の表示に影響を与える要素となるため、意図せず興味のないユーザーが提案されるケースもあるのです。
アルゴリズムがユーザーに与える影響
X(旧Twitter)のアルゴリズムによる表示は、新たな人とのつながりを広げるきっかけになる一方で、無関係なアカウントの表示によってタイムラインの見づらさを招く場合もあります。
たとえば、話題性のあるアカウントやフォロワー数の多いユーザーが頻繁に表示されると、タイムラインの内容が偏ったものになり、利用者にとってノイズとなることがあります。
そのため、自分が本当に必要とする情報や関心のあるアカウントに集中できるよう、表示内容を定期的に調整していくことが重要です。
興味関心の設定を見直したり、表示されたアカウントを手動で「表示しない」に設定したりすることで、少しずつアルゴリズムの提案内容を最適化することが可能です。
自分に合った情報だけを効率よく受け取るためには、能動的に設定を見直し、不要な表示を減らしていく工夫が欠かせません。
まとめ
スマホ版X(旧Twitter)の「Who to Follow」表示は、設定の見直しや興味関心の調整によってある程度非表示にできます。
完全に表示を消すことは難しいですが、今回紹介した設定や対策を活用すれば、表示頻度を大きく減らすことが可能です。
より快適なX(旧Twitter)体験を目指して、必要な設定を行ってみましょう。