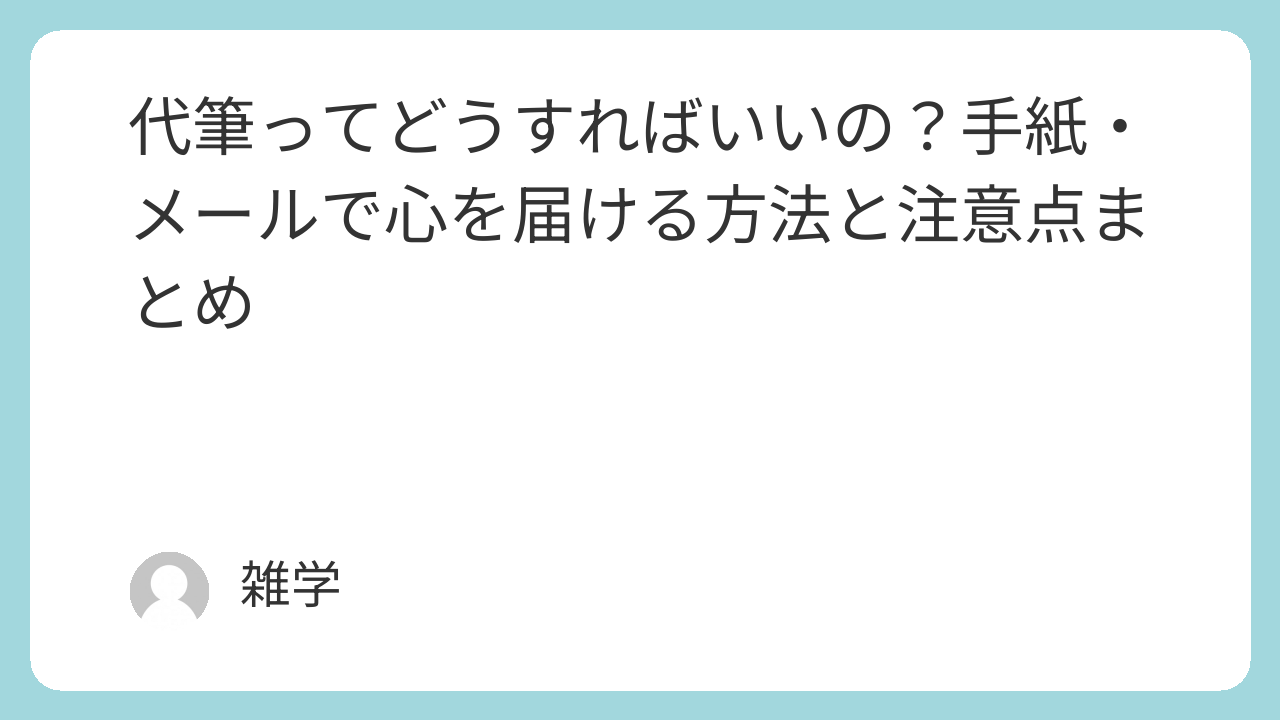この記事では、誰かの気持ちを代わりに伝える「代筆」の方法やマナーについて、やさしく丁寧に解説します。
手紙やメールなど、言葉で想いを伝えたいけれど、どうしても本人が書けない──そんなときに必要になるのが代筆です。
「どう書けば失礼じゃない?」「本人の気持ちってどう表せばいい?」と迷う方も多いはず。
この記事では、代筆が必要になるシーンから、実際の書き方、マナー、デジタル時代の工夫まで、初心者の方にもわかりやすくまとめました。
大切な人の気持ちをやさしく丁寧に届けたい方に、ぜひ読んでいただきたい内容です。
代筆とは?基本の意味と使われるシーン

代筆の定義と「代理」との違い
代筆とは、本人に代わって誰かが手紙や文章を書くことを指します。
つまり、文字を書くという行為を代行することが代筆の本質です。
よく似た言葉に「代理」がありますが、代理はその人の立場や意思を代わって行動することを意味します。
たとえば契約を代理で結ぶなど、行動や判断まで代わるのが「代理」です。
一方、代筆はあくまで「本人の気持ちを表現するお手伝い」という位置づけで、意思決定そのものを代わるものではありません。
本人が伝えたい内容や感情を、できるだけ忠実に、やさしい言葉で書き起こす役割が求められます。
手紙・メール・書類など代筆が必要な場面とは?
けがや病気、高齢で字が書けない方の代わりにご家族が手紙を書くケースや、小さな子どものお礼状、ビジネス上のフォーマルな文書など、幅広い場面で代筆は求められます。
本人の想いを正しく伝えるためには、ただ書くだけでなく、その背景や相手との関係性を踏まえて内容を整えることが大切です。
たとえば、お見舞いのお礼や季節のご挨拶、弔電、祝い状などでは、形式と気持ちのバランスも必要です。
その人の思いを適切に伝えるために、代筆の技術と配慮が重要になります。
本人の想いを代筆で伝えることの重要性
代筆は、単に文章を書く作業ではなく、相手に届けたい「気持ち」や「思い」を言葉にして表現する大切な手段です。
たとえば「ありがとう」や「元気です」といった短い一文でも、背景にある気持ちを汲み取りながら表現することで、読む人の心に深く届きます。
代筆する側の思いやりや、言葉の選び方ひとつで、文章の印象が大きく変わることもあります。
丁寧に心を込めて書くことで、受け取る側にも温かさや誠実さが伝わります。
文字にすることで、伝えたい気持ちをカタチにできるのが代筆の魅力です。
代筆が必要になる具体的なケース一覧

高齢・病気・ケガなどで本人が書けない場合
年齢を重ねていくと、手が震えたり、視力が落ちたりして文字を書くのが難しくなることがあります。
また、ペンを握ること自体が困難になるケースも少なくありません。
病気で長く寝たきりの状態が続いている方の場合、体調は安定していても、文章を書くという作業が思うようにできないことがあります。
そのようなとき、周囲の家族や介護者が代筆をして、本人の気持ちを形にしてあげることが大きな助けになります。
手紙やお礼状、季節のご挨拶、入院中のお知らせなど、代筆によって人とのつながりが保たれることも多く、心の支えになる場合もあります。
子どもや家族の代筆|保護者・家族代表として書くとき
小さな子どもがまだ字を書けない年齢である場合や、ひらがなで書いたとしても意味が十分に伝わりにくい内容の場合には、保護者が代筆することがよくあります。
また、家族の代表として文書を提出するとき、たとえば学校への欠席連絡や、地域の行事への参加のお知らせなどでも、代筆が必要になることがあります。
「子どもが心をこめて言いたいこと」をなるべく素直な言葉で書くように心がけると、読む側にもやさしい印象を与えることができます。
本人の口調を意識した一文を加えるだけでも、その子らしさが伝わり、温かみのある手紙になります。
職場やビジネスシーンで代筆が求められる場面
職場では、体調を崩している上司や同僚の代わりに、メールや手紙を送らなければならない場面が発生することがあります。
たとえば、入院中の上司の代筆でお礼状や年始のご挨拶を送る場合や、取引先への連絡文書を代筆する場合などです。
このようなときには、本人の口調や社内での立場を意識し、文面に不自然さが出ないように気を配る必要があります。
代筆であることを伝える一文を添えると同時に、相手への配慮や丁寧な印象が伝わるような文面に仕上げることが大切です。
シーン別・実践的な代筆文例集【テンプレ付き】

家族の代筆メッセージ|子ども・親・祖父母
「おじいちゃん、いつもありがとう。ぼくはげんきです。またあそびにいくね。○○(本人の名前)より」
おじいちゃんやおばあちゃんに向けた手紙は、素直であたたかい表現が喜ばれます。
文章は短くても構いませんので、「会いたい気持ち」「ありがとうの気持ち」などをやさしく込めてあげましょう。
子どもらしさが感じられる言葉を使うと、より印象に残る手紙になります。
※代筆者名は文末に「(代筆:母)」などの形で記載します。
必要に応じて「○○が伝えたいことを代筆しています」と冒頭に書いても丁寧です。
職場での代筆メール|上司・部下・休職中の同僚に
「○○は現在療養中につき、私△△が代わりにご連絡差し上げます。○○からは『ご迷惑をおかけし申し訳ありません』との伝言を預かっております。」
職場での代筆は、ビジネスマナーを意識しながらも、本人の口調や社風に合わせて書くことがポイントです。
とくにメールの場合は、件名や署名にも代筆である旨を明記すると混乱がありません。
また、やり取りが何度か続く場合は、誰がどこまで代筆しているかをはっきりさせておくと、誤解を防ぐことができます。
お礼状・季節の挨拶・冠婚葬祭の代筆文例
「拝啓 爽やかな季節となりました。さて、父○○は現在入院中のため、私△△が代筆にてご挨拶申し上げます。皆さまには平素よりご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。」
フォーマルな手紙を代筆する場合は、文章の形式や時候の挨拶を整えつつ、相手への感謝や敬意がきちんと伝わる内容にすることが大切です。
本人の体調や状況をさりげなく伝えながら、代筆であることも明確に書いておくと安心感があります。
必要に応じて「本人の了承を得て、代筆しております」などの一文を添えると、誠意がより伝わります。
代筆を頼むとき・頼まれたときのマナーと対応

代筆をお願いするときの丁寧な言い方とタイミング
「お手数をおかけしますが、代わりに書いていただけますか?」や「ご迷惑でなければ、文章を書いていただけると助かります」といった、相手を思いやる言葉を添えてお願いするのが基本です。
特に親しい間柄でも、丁寧な言葉づかいを心がけることで、気持ちよく引き受けてもらいやすくなります。
感謝の気持ちは、お願いする前にも後にも必ず伝えるようにしましょう。
また、急ぎの場合であっても「申し訳ないのですが、至急このような事情があり…」と背景を説明して、相手に無理をさせないように配慮することが大切です。
時間に余裕があるときには、下書きを用意したり、本人の口調や伝えたい内容を簡単にまとめておくと、お願いされた側も書きやすくなります。
代筆を頼まれたときの断り方|気まずくならない表現
代筆を頼まれても、どうしても引き受けられない事情がある場合は、無理をせず、正直に断って構いません。
たとえば「申し訳ありませんが、気持ちをうまく表現できるか自信がなくて…」といったように、相手の立場を尊重しながら自分の気持ちを伝えましょう。
断る際には、「○○さんの気持ちはきちんと伝えたほうが良いと思うので、他の方にお願いしてみてはどうでしょうか」と代替案を示すと、やわらかい印象になります。
気まずさを避けるためにも、相手との関係を大切にする姿勢が伝わるよう、あたたかい言葉選びを心がけてください。
内容に違和感があるときの確認方法・トラブル防止策
代筆中に、文面に違和感を覚えたり、表現が強すぎる・曖昧すぎると感じた場合には、「この表現で本当に大丈夫ですか?」「もう少し柔らかい言い方にしてもいいですか?」など、遠慮せずに確認することが大切です。
本人がどのような気持ちで書こうとしているのかを確認することで、より正確に気持ちを反映した文章にすることができます。
特に大切な手紙やフォーマルな場面での文書の場合は、書き終わった後に本人に読み上げて確認してもらう、または一緒にチェックする時間を取るようにすると安心です。
このひと手間が、誤解やトラブルを防ぎ、信頼される代筆につながります。
正しい代筆マナーと心に届く文章表現

代筆者を明記する際の書き方・文末例
「(代筆:長女 △△)」など、誰が書いたのかわかるように文末に記載します。
これは受け取った相手にとって、文章が誰の言葉であり、誰が代筆したのかを明確にする大切な情報です。
とくにフォーマルな場面やビジネスのやり取りでは、情報の正確さと信頼性が重視されるため、代筆者の明記はマナーの一環とされています。
個人間のやり取りであれば、簡単な署名や「母より」「○○(家族の名前)代筆」などでも十分ですが、
公式な書類やご挨拶状などでは「本人の名前+代筆者名(関係性)」という形が望ましいです。
例:
○○ ○○(本人)
(代筆:長女 ○○ ○○)
また、文中や文末に「○○の意向に基づき、代筆しております」などの一文を添えることで、より丁寧な印象になります。
本人の言葉を尊重した文体を意識しよう
代筆する際に気をつけたいのは、自分の文体になりすぎないことです。
「本人ならこう言いそうだな」「普段こんな言い回しをするな」と想像しながら、言葉を選ぶようにしましょう。
特に親しい間柄では、堅苦しくしすぎず、普段の会話の延長のような文章にすることで、より自然に伝わります。
逆に、フォーマルなシーンでは、丁寧語や敬語を加えながらも、過剰にならないようにバランスを取りましょう。
誤解を招かない敬語・丁寧語の選び方
丁寧な言葉づかいは、代筆文の基本です。
しかし、敬語を使いすぎると相手に距離を感じさせてしまったり、不自然な文章になることがあります。
敬語と丁寧語のバランスを意識しつつ、読み手にやさしく伝わる文体を心がけましょう。
また、二重敬語や回りくどい表現は避け、スッキリと読みやすい構成を目指すと好印象です。
感情をこめたいときの言葉選びのコツ
「ありがとう」「ごめんなさい」「うれしい」など、感情を表す言葉はとても大切です。
ただ単に伝えるだけではなく、「本人の気持ちがここにある」ということを読み手に感じてもらえるよう、少しだけ本人らしい言い回しを加えてみましょう。
たとえば「お元気ですか?」の一言でも、「○○さん、寒くなりましたがお元気ですか?」と季節感を加えるだけで、ぐっと温かさが伝わります。
感情の押しつけにならないように、あくまでさりげなく、相手のことを思いやる表現にまとめるのがポイントです。
デジタル時代の代筆術|メール・SNSでの配慮ポイント

メールで代筆するときの基本マナー
冒頭に「○○に代わり、△△が送信しております」や「○○の依頼により、△△が代筆しております」などと明記するのがマナーです。
誰が書いているのかを明確に伝えることで、受け取った相手が混乱するのを防ぎ、誤解を避けることができます。
署名欄にも代筆者の名前と役職(必要であれば)を添えることで、より信頼感のある印象になります。
例)
(代筆:△△ △△/総務部)
ビジネスシーンでは、件名にも「(代筆)」や「代理送信」といったキーワードを入れておくと、やり取りがスムーズになります。
返信を求める場合には、返信先が本人か代筆者かを明示しておくと親切です。
SNSメッセージ代筆の注意点(LINE・DMなど)
LINEやDMなどのSNSで代筆を行う際も、「代筆です」「○○に頼まれて送っています」といった一言を添えることで、誠実な印象になります。
特にスタンプや短文が中心のやりとりでは、誰のメッセージかが曖昧になりがちなので、文頭か文末に明記するのが安心です。
また、代筆であることを曖昧にしたまま送ると、後で誤解を生んでしまう可能性もあるため、気をつけたいポイントです。
急な連絡や返信代行でも、誰が書いているかを明確にしましょう。
デジタル代筆ならではの追加配慮事項
スマホやパソコンで打つ文章は、感情が伝わりにくく、冷たく感じられることがあります。
そのため、句読点の打ち方や語尾の工夫、絵文字や顔文字を適度に使うなど、やさしい印象を与える工夫が大切です。
たとえば「よろしくお願いします」だけで終わらせず、「よろしくお願いします😊」や「お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします」など、やわらかい言い回しを心がけましょう。
スタンプを使う場合も、本人が普段どんなスタンプを好んで使っているかに合わせて選ぶと、より自然で違和感のないやり取りになります。
文章だけでなく「その人らしさ」も大切にできるのが、良いデジタル代筆のコツです。
よくある疑問Q&A|代筆の不安や迷いを解消しよう
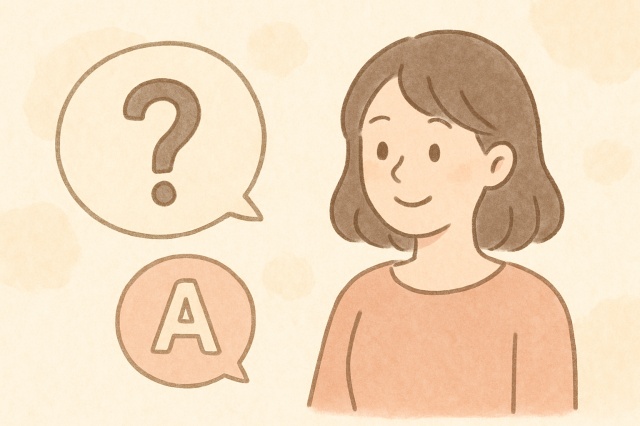
代筆と代理の違いって何?
代筆は「文章だけ」を書く行為で、意思決定には関与しません。
代理は「行動や判断」も代わって行うことです。
代筆がバレたら失礼になる?正直に書いてOK?
代筆であることは明記したほうが相手にとっても安心です。
誠実さが伝われば失礼にはなりません。
感情を込めた表現はやりすぎ?
本人が伝えたい気持ちであれば、やさしい言葉で表現して問題ありません。
ただし、過剰に盛りすぎないように注意しましょう。
【チェックリスト】代筆する前に確認すべき5つのこと
- 手紙を書く目的(お礼・お詫び・挨拶など)や相手の立場、送る時期や状況が明確になっているか?
-
本人の気持ちや伝えたいメッセージを、事前にしっかりヒアリングできているか?
会話やメモを通して、本人の言葉や口調をなるべく正確に把握しておくと安心です。 -
文章に不自然な敬語や、相手に誤解を与えるような表現が含まれていないか?
文章のトーンや丁寧さに違和感がないかを見直しましょう。 -
書こうとしている手紙やメールが、代筆であることを明記すべき性質の文書かどうか?
特にビジネスやフォーマルな場面では明記が必要です。 -
書き終えた内容を、必ず本人に確認してもらい、必要があれば修正を加える時間を確保しているか?
最後のチェックは、本人の気持ちを反映できているかどうかの大切なポイントです。
まとめ|代筆だからこそ伝わる、心のこもった文章を大切に
代筆は、誰かの「声」や「気持ち」を文章で届けるやさしい行為です。
形式やマナーも大切ですが、一番大切なのは、想いをまっすぐに届けること。
読む人の心にそっと寄り添う、そんな代筆ができると素敵ですね。