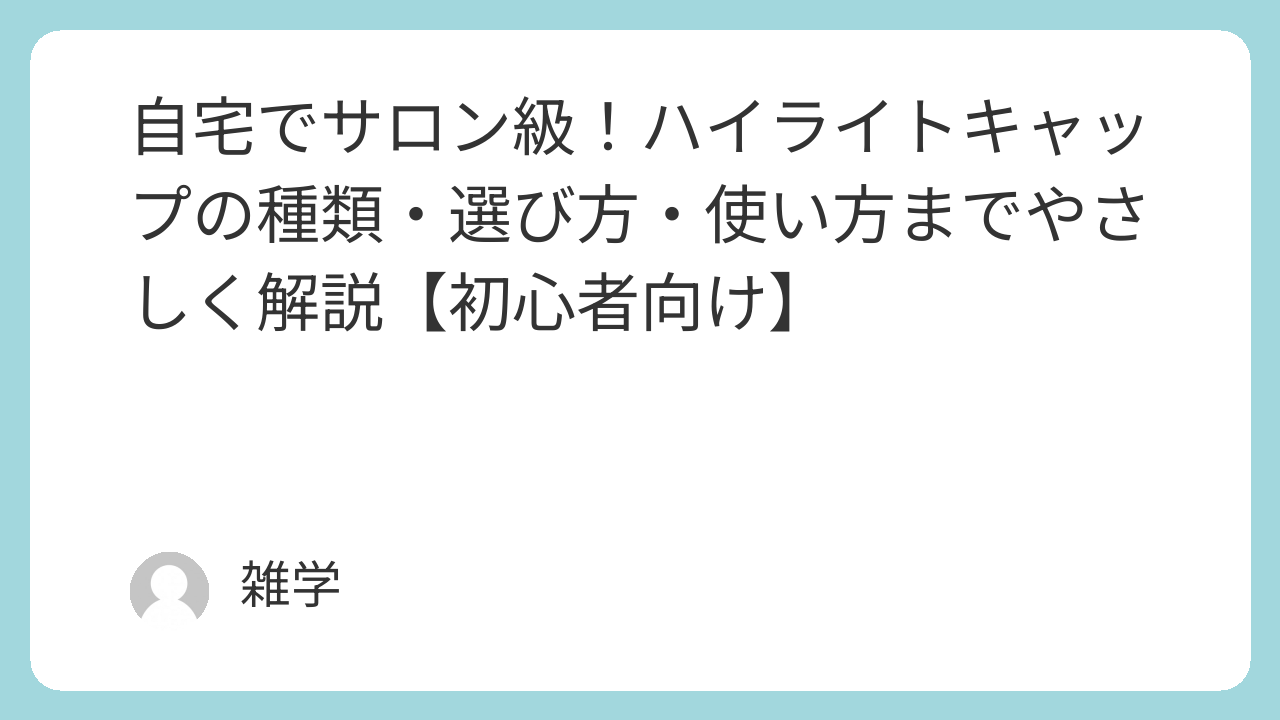自宅でサロン風のヘアカラーを楽しみたい方にぴったりなのが「ハイライトキャップ」。
カラー初心者さんでも扱いやすく、必要な部分だけにカラーを入れられる便利なアイテムです。
全体を染めるのはちょっと不安…という方や、髪へのダメージを最小限に抑えながら印象を変えたい方にもおすすめです。
この記事では、ハイライトキャップの基本的な仕組みから種類、選び方、使い方のコツまでをやさしく解説していきます。
使ってみたいけど失敗が怖い、どう選べばいいのかわからない…という方でも安心して読み進められるように、丁寧に紹介していきます。
カラー剤や使いやすい道具の情報、SNSで話題の商品、よくあるトラブルと対処法まで網羅しているので、セルフカラーの入門ガイドとしてぜひ参考にしてください。
ハイライトキャップとは?仕組みと特徴をやさしく解説
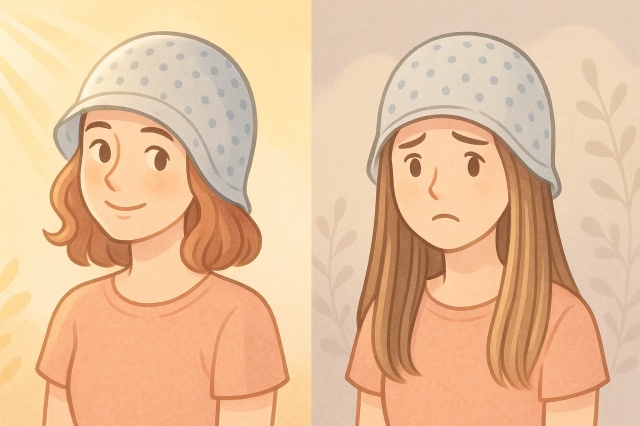
ハイライトキャップは、髪の毛の一部だけを染めるために使う道具です。
キャップを頭にかぶり、小さな穴から細い毛束を引き出してカラー剤を塗布します。
全体を染めるよりも自然な立体感が出るのが特徴です。
カラー初心者さんでも扱いやすく、自宅でのセルフカラーにぴったりなアイテムです。
部分染めを自然に仕上げる理由
ハイライトキャップでは、キャップから出した毛束の部分だけにカラー剤を塗布するため、元の髪色とのコントラストが自然に仕上がります。
そのため、境目が目立ちにくく「いかにも染めました」という印象を避けられます。
自然光の下でも目立ちすぎず、さりげなく印象を変えられるのが魅力です。
特にナチュラルな雰囲気を大切にしたい方には、とても使いやすい方法と言えるでしょう。
部分的に色を加えることで、髪に奥行きややわらかさが加わり、ヘアスタイル全体のバランスがよくなります。
全体カラーとの違いとメリット
全体カラーは髪全体を均一に染めるため、色ムラが出にくく、統一感のある仕上がりになりますが、のっぺりとした印象になることもあります。
一方、ハイライトキャップを使えば、部分的に明るさを加えることで髪に動きと立体感が生まれ、軽やかな印象に変わります。
また、染める面積が少ないため、髪全体にかかるダメージも抑えられ、繰り返しカラーをしても傷みにくいというメリットがあります。
伸びてきた根元との境目も自然になじむため、頻繁に染め直す必要がないのも嬉しいポイントです。
どんな人におすすめ?
にとって、ハイライトキャップは心強い味方になります。
ハイライトキャップのメリット・デメリット
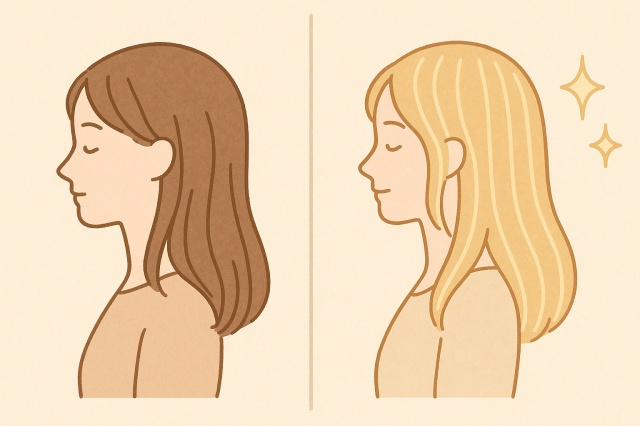
ハイライトキャップには良い点もあれば、注意すべき点もあります。
正しく使えば、自宅でもサロンのような仕上がりが目指せます。
髪を傷めにくい仕組みとは?
ハイライトキャップは、髪の一部分だけをカラーリングする仕組みなので、全体染めよりも圧倒的にダメージを抑えられます。
具体的には、キャップを被って小さな穴から必要な分の毛束だけを外に出し、その部分だけにカラー剤を塗布します。
これにより、髪の広範囲に薬剤が触れることがなく、ダメージが集中するのを避けられます。
結果として、カラーによる乾燥やパサつきが起こりにくく、髪本来のツヤやまとまりを保ちやすいのが大きなメリットです。
また、カラー剤を塗る範囲が限定されていることで、カラー剤の使用量も少なく済み、経済的にも負担が軽減されます。
ヘアケアを大切にしたい方には、とてもおすすめの方法です。
セルフカラーで使うメリット
美容院に行くには時間やお金がかかりますが、ハイライトキャップを使えば、自宅にいながら自分のペースでカラーリングが楽しめます。
わざわざ予約を取ったり、長時間待ったりする必要がなく、家事の合間や空いた時間に気軽に挑戦できます。
また、セルフカラーに不慣れな方でも、キャップを使えば塗布する範囲が決まっているので、失敗のリスクも減らせます。
最近では、カラー剤とセットになった便利な商品も多く販売されており、初めての方でも手軽にチャレンジできる環境が整っています。
動画やSNSで使い方をチェックしながら進められるのも安心ポイントです。
注意すべきリスクと失敗例
ハイライトキャップを使ううえで注意したいのは、髪を穴から引き出すときの力加減とバランスです。
うまく引き出せなかったり、無理に引っ張ってしまうと毛束が不自然な位置から出てしまったりすることがあります。
また、毛束の量が多すぎたり、位置が偏ってしまうと、仕上がりにムラが出てしまい、全体のバランスが崩れてしまいます。
さらに、染まり具合を確認せずに長時間放置すると、明るくなりすぎてしまったり、ダメージが出る原因になります。
カラー剤の放置時間は商品ごとの説明に従い、こまめに確認することが大切です。
不安な場合は、最初は短めの時間で試し、様子を見ながら少しずつ時間を延ばすと安心です。
使い終わった後は、キャップの洗浄や保管も忘れずに行いましょう。
ハイライトキャップの種類と素材別の違い

市販されているハイライトキャップには、さまざまな素材や形状があります。
自分に合ったものを選ぶことで、使いやすさがぐんとアップします。
シリコン製・ビニール製・使い捨ての特徴と比較
シリコン製は柔軟性とフィット感に優れており、頭の形にぴったり沿うのでズレにくいのが特長です。
カラー中に動いてもズレにくいため、安心して作業を進めることができます。
洗って繰り返し使えるので、コスパ面でも優れており、環境にもやさしい選択肢です。
また、しっかりした作りのものが多いため、プロ仕様に近い使い心地を求める方にもぴったりです。
ビニール製は非常に軽くて柔らかく、扱いやすい点が魅力です。
初めての方でも気軽に試しやすく、価格も比較的お手頃なものが多いのが特徴です。
ただし、耐久性ではシリコン製にやや劣る場合もあるため、使い捨て感覚で数回の使用を想定すると良いでしょう。
柔らかくて頭に沿いやすいので、着脱がスムーズに行えるのもメリットです。
使い捨てタイプは衛生的で、1回使い切りなのでお手入れが不要なのが大きなポイントです。
旅行先や出張中にカラーをしたい時や、「まずは試してみたい!」というお試し用途におすすめです。
枚数が多く入ったセットも販売されており、コスパ重視の方にも人気です。
ゴミが出る点には配慮が必要ですが、時間や手間をかけずに使える便利な選択肢です。
初心者向けとプロ仕様の違い
初心者向けのキャップは、穴が比較的大きめに設計されており、髪の毛を引き出しやすくなっています。
また、穴の数も少なめに設定されているものが多く、作業がスピーディーに済むようになっています。
素材も柔らかく、頭にフィットしやすいため、セルフカラーに慣れていない人でも大丈夫です。
一方、プロ仕様のキャップは、細かなハイライトを正確に入れたい方におすすめです。
穴の間隔が均一で数も多く、自由度の高いハイライトデザインが可能です。
素材もしっかりしていて耐久性が高く、繰り返しの使用にも適しています。
カラーの仕上がりにこだわる方や、美容師さんが使用するような本格的なアイテムを求める方に最適です。
フィット感や耐久性の違いとは?
フィット感が良いキャップを選ぶことで、染めムラが起こりにくくなり、均一で美しいハイライトに仕上がります。
頭にしっかりと沿う形状や伸縮性のある素材を選ぶことで、長時間の施術でも滞りなくなく作業できます。
耐久性については、何度も使う予定がある場合はシリコン製などのしっかりした素材が安心です。
一方、ビニール製や使い捨てタイプは軽量で柔らかい分、数回の使用で破れやすくなることもあるため、用途や頻度に応じて選ぶことが大切です。
また、使用後の手入れのしやすさや収納のしやすさも、長く快適に使うためのポイントになります。
美容院用とセルフ用キャップの違いを解説

美容師さんが使うキャップと市販のセルフ用キャップには違いがあります。
どちらが自分に合っているか、特徴をチェックしましょう。
プロ仕様キャップの特長と使い方
プロ仕様のハイライトキャップは、素材の質が高く、しっかりとした厚みと張りのある作りになっています。
そのため、頭の形にしっかりフィットしやすく、カラー剤の液ダレやズレを防ぎながら正確に作業を進めることができます。
さらに、穴の配置が均等で数も多いため、細かいハイライトを計画的に入れたい方にぴったりです。
美容師さんがサロンで使用しているようなプロフェッショナル仕様なので、施術時間が長くなる場面でも快適に使えます。
耐久性も高く、繰り返し使っても形崩れしにくいのも魅力です。
自分で本格的にヘアカラーを楽しみたい方や、美容の仕事をしている方にも人気があります。
セルフ用キャップの使いやすさとおすすめタイプ
セルフ用キャップは、使いやすさと手軽さを重視したデザインになっているものが多いです。
特に穴の間隔が広めで、髪を引き出す作業がしやすいように設計されています。
初めてハイライトに挑戦する方や、不器用で細かい作業が苦手な方でも安心して使えるのが大きな魅力です。
また、素材がやわらかく頭にフィットしやすいため、長時間の使用でもストレスを感じにくい設計になっています。
家庭用としてはもちろん、ちょっとした気分転換やイベント前のおしゃれにもぴったりです。
近年では100円ショップやネット通販でも気軽に手に入るようになり、人気が高まっています。
どっちを選ぶべき?選び方のポイント
自分の技術レベルや、どんな仕上がりを目指したいかによって選ぶのがおすすめです。
慣れてきたら、セルフ用からプロ仕様にステップアップするのもひとつの方法ですよ。
ハイライトキャップはどこで買える?購入方法まとめ

身近なお店でもネットでも購入可能です。
選び方のポイントをおさえて、自分にぴったりの1枚を見つけましょう。
実店舗で買えるお店(ロフト・ドンキなど)
ハイライトキャップは、ロフトや東急ハンズ、ドン・キホーテといったバラエティショップをはじめ、マツモトキヨシやウエルシアなどのドラッグストア、美容専門用品を扱う店舗などで手に入ります。
これらの実店舗では、商品を実際に手に取って確認できるのが大きな魅力です。
素材の厚みや柔らかさ、サイズ感、キャップの穴の大きさや間隔など、ネットでは分かりにくい細かな違いをしっかりチェックできます。
また、スタッフがいれば相談に乗ってくれることもあるため、初心者にとっては安心感があります。
実店舗によっては、カラー剤と一緒にセット販売されていることもあり、気になる商品をその場で比較しながら選べるのもメリットです。
急ぎで必要な場合や、試してから購入したい場合には、実店舗での購入がおすすめです。
ネット通販での選び方と注意点
ネット通販では、ハイライトキャップの種類やデザイン、価格帯が非常に豊富に揃っています。
特にAmazonや楽天などでは、カラー剤とのセット商品、専用のフック付き商品、プロ仕様タイプなども充実しています。
購入する際は、レビューや評価をよく確認することが大切です。
初心者向けか、プロ仕様かといった詳細が記載されているかもチェックポイントです。
また、販売元が信頼できるかどうかや、返品・交換の可否も確認しておくと安心です。
配送に日数がかかることもあるので、特にイベントや旅行前などに使用したい場合は、余裕をもって注文することをおすすめします。
送料無料やタイムセールなどを活用すれば、お得に購入できることもあります。
人気ショップ&価格帯一覧
・Amazon:800円〜2,000円台まで豊富。レビュー数も多く、初心者用からプロ仕様まで幅広いラインナップ。
・楽天:セット商品やレビュー多数。コーム付き、カラー剤付きのセットも豊富で比較しやすい。
・Yahoo!ショッピング:割引やクーポンが頻繁に出るため、タイミングによってはかなりお得に購入可能。
・Qoo10:韓国製の人気商品も多く、独自セールも狙い目。
・公式オンラインショップ:FramarやWellaなど、特定ブランドを狙いたい方にはおすすめ。
初心者向け!ハイライトキャップの選び方ガイド

初めて使う方こそ、選び方がとても大切です。
ポイントを押さえれば失敗のリスクも減らせます。
はじめての人におすすめのタイプ
初めてハイライトキャップを使う方にとっては、「失敗しにくく扱いやすいこと」が何よりも大切です。
穴の数が少なめで、柔らかい素材のキャップは、頭にフィットしやすく髪を引き出す作業もスムーズです。
穴が大きめに設計されているタイプを選ぶと、細かな作業が苦手な方でも扱いやすく、ストレスを感じにくくなります。
また、あらかじめ目立ちにくい部分だけにハイライトが入るような設計のキャップもあり、初心者には安心です。
染まりすぎが心配な方は、細いハイライト向けに穴の間隔が広めで、毛束が少量ずつ取り出せるタイプを選ぶと失敗を防げます。
使い方がわかりやすい説明書付きの製品や、YouTubeやSNSでレビューされている商品も安心感があります。
髪質・毛量別に選ぶポイント
髪が細くて柔らかい方は、キャップがずれにくいシリコン製がぴったりです。
フィット感が高いため、引き出した毛束の位置が安定し、染めムラのリスクが減ります。
反対に、髪が太くてしっかりしている方や、毛量が多めの方は、穴数が多めで柔軟な素材のキャップがおすすめです。
一度にたくさんの毛束を出せるタイプなら、時間短縮にもなりますし、全体のバランスも取りやすくなります。
クセ毛の方やロングヘアの方は、穴の間隔が広すぎないキャップを選ぶと、仕上がりがきれいに整います。
価格・使いやすさ・コスパで比較
「とりあえず一度試してみたい!」という方には、使い捨てタイプが手軽でおすすめです。
価格も手ごろで、1回限りの使用でも惜しくないため、まずはお試し感覚で挑戦しやすいです。
長く使いたい場合や、何度もセルフカラーを楽しみたい方には、洗って再利用できるタイプが断然お得です。
シリコン製などの耐久性の高い素材は、数回の使用にも耐え、長い目で見ればコストパフォーマンスに優れています。
また、カラー剤とセットになっている商品や、フック付きで操作が簡単なアイテムなどもコスパの観点で魅力的です。
どこまでの仕上がりを求めるか、使用頻度や予算に合わせて、ぴったりのキャップを選びましょう。
人気ブランド&おすすめ商品まとめ

実際に使ってみて評価が高い商品をご紹介します。
耐久性重視!プロ仕様の定番ブランド
・Wella(ウエラ)
・Framar(フラマー)
これらのブランドは、実際に多くの美容室でも使われている高品質な製品を提供しています。
Wellaは長年にわたる信頼と実績があり、カラー剤との相性も良く、使いやすさと耐久性に定評があります。
Framarはおしゃれでカラフルなデザインが人気で、機能性も抜群。
キャップ以外にも、カラーリング用のコームやブラシ、ケープなども取り扱っており、プロが愛用する理由がよく分かります。
どちらも再利用が可能で、しっかり洗って乾かせば長く使えるため、頻繁にセルフカラーを楽しむ方にもおすすめです。
コスパ抜群!セルフカラー向けおすすめ商品
レビューや口コミを見ながら選べるのも安心ポイントです。
送料無料や割引クーポンが使えるショップも多く、コスパ重視の方に特に人気です。
コームやカラー剤付きの便利なセット商品も
ハイライトに必要なアイテムがセットになっていると、初めての方でも迷わずに始められます。
たとえば、キャップに加えてフック・コーム・手袋・ケープなどがセットになった商品は、準備がスムーズで手間がかかりません。
特に「はじめてのハイライトセット」や「初心者向けフルキット」などの名前で販売されている商品は、説明書付きで安心です。
カラー剤と合わせて購入できるタイプも多く、必要なものがすべて揃っているのは忙しい方にも嬉しいポイント。
見た目もおしゃれなパッケージのものが増えているので、プレゼントや友達とのシェアにもおすすめです。
セルフカラーでの使い方ガイド

いざ使ってみようと思っても、不安な方も多いはず。
基本的な使い方の流れをご紹介します。
初めてでも失敗しない使い方の手順
-
キャップをしっかり被る
キャップの前後を間違えないように確認しながら、頭全体を包むようにしっかり装着します。
髪が全体的にキャップ内におさまっているか、鏡でチェックしながら丁寧に整えましょう。
髪が乾いた状態のほうが引き出しやすいですが、静電気が気になる場合は少しだけ水で湿らせてもOKです。
-
付属のフックで穴から髪を引き出す
キャップの小さな穴にフックを差し込み、髪の束を少量ずつ外に出します。
一度に多く引き出そうとせず、左右均等にバランスよく出すことで仕上がりが自然になります。
無理に強く引っ張らず、ゆっくり優しく行いましょう。
-
カラー剤を塗布
引き出した毛束にカラー剤をムラなく塗ります。
根元から毛先まで均一になるように意識し、コームやブラシを使うとよりきれいに仕上がります。
手袋をつけて行い、周囲が汚れないように新聞紙や古いタオルなどで保護するのもおすすめです。
-
指定の時間放置
カラー剤の説明書に記載された時間を参考に放置します。
途中で色の入り具合を確認したい場合は、1束だけ拭き取ってチェックするのが安心です。
室温や髪質によって染まり方が異なるため、初めてのときはこまめに様子を見ると良いでしょう。
-
よく洗い流す
時間になったらキャップを外し、ぬるま湯で髪をしっかりすすぎます。
その後、シャンプーとトリートメントを使って、髪と頭皮をやさしくケアしましょう。
ハイライトを入れるおすすめの位置・バランス
・顔周り:顔の輪郭を明るく見せ、印象を華やかにしてくれます。
・トップ:頭頂部に動きと立体感が出て、ヘアスタイルがふんわり軽やかになります。
・毛先:毛先だけに入れると、グラデーションのようなナチュラルな仕上がりに。
この3つのポイントを意識することで、初心者でも失敗しにくく、こなれ感のあるハイライトが完成します。
いずれも左右対称になるように入れると、全体のバランスが整います。
使用後の洗浄・乾燥・保管のポイント
再利用する場合は、カラー剤が付着した部分をすぐにぬるま湯で洗い流し、やさしく中性洗剤で洗ってください。
キャップの内側やフックの先端までしっかり洗浄すると、次回も使えます。
乾燥させるときはタオルで水気を拭き取り、風通しの良い場所で自然乾燥させましょう。
乾燥後はキャップの形を保ったまま、折りたたまずに保管するのが理想です。
引き出しの中や、フックと一緒に収納できる専用ケースがあると便利です。
長く使いたい場合は、保管時に重みのかかる場所を避け、変形を防ぐ工夫も大切です。
ビフォーアフターで見る!仕上がりの違い
ハイライトキャップを使うと、印象ががらりと変わります。
ハイライトなし/ありの印象比較
なし:全体がフラットで単調な印象になりやすく、髪の動きや立体感が見えづらいため、少し重たく感じることもあります。
あり:ハイライトが入ることで、髪に自然な陰影ができ、ふんわり軽やかに見せることができます。
とくに光が当たったときに明暗の差が際立ち、髪全体にツヤと動きが加わるため、顔まわりも明るい印象に変化します。
さりげない変化ながら、スタイルに立体感を持たせたいときにぴったりのテクニックです。
太め・細めハイライトでどう変わる?
太め:しっかりとした存在感があり、外国人風のラフでカジュアルな雰囲気を演出できます。
大胆な印象になるため、トレンド感を出したいときや、ストリート系・ボヘミアン系ファッションとの相性も抜群です。
スタイルにインパクトを持たせたい方や、イメージチェンジを狙いたい方におすすめです。
細め:繊細でナチュラルな仕上がりになり、やわらかく上品な印象を与えてくれます。
オフィススタイルやナチュラルメイクとの相性も良く、幅広い年代の女性に人気です。
髪を巻いたときにも自然な陰影が出て、立体感とツヤ感がアップします。
全体カラーとの立体感の差とは?
全体染めは髪全体に均一な色が入るため、ツヤ感は出やすい一方で、のっぺりとした印象になりがちです。
一方、ハイライトを入れることで明るい部分と暗い部分がミックスされ、光の当たり方によって髪が動いて見えるようになります。
顔の輪郭や表情にも明暗がつきやすくなり、メリハリのある印象になります。
特にミディアム〜ロングヘアの方にとっては、スタイル全体の軽さを演出できる有効なテクニックと言えるでしょう。
よくある失敗と対処法
事前に知っておくと、慌てずに対応できます。
髪がうまく引き出せないときの対策
フックの角度を変えるだけでも、髪を引き出しやすくなることがあります。
特に、頭皮に対して垂直ではなく、少し斜めに差し込むようにすると毛束が自然に出てきやすくなります。
また、髪が乾燥しすぎていると引っ張りにくくなるため、霧吹きで軽く湿らせてから作業するとスムーズです。
髪が絡んでしまう場合は、先にブラッシングしておくと引き出しやすくなります。
それでも難しい場合は、穴の大きさが広めのキャップや、穴の位置がわかりやすい色付きタイプに変えてみるのもおすすめです。
染まりすぎ・ムラになる原因と解決策
カラー剤の量が多すぎたり、偏って塗布してしまうと、部分的に濃く染まってしまいムラになります。
逆に量が少なすぎると、染まりが浅くなり色の差が分かりにくくなるため、適量を意識することが大切です。
一度にたくさん塗ろうとせず、少しずつ丁寧に重ねるように塗布すると、自然な仕上がりになります。
また、放置時間が長すぎると予定よりも明るくなりすぎたり、髪が傷む原因にもなるので、時間はタイマーでしっかり管理しましょう。
塗り始めた時間と放置終了時間をメモしておくと安心です。
カラー剤を塗る順番にも注意し、均等な時間で色が入るように心がけるとムラを防げます。
キャップがきついときの工夫
キャップが小さすぎる場合は、やわらかく伸縮性のある素材に変えると、頭の形に優しくフィットしやすくなります。
市販の帽子型のハイライトキャップや、締め付けの少ないゆったりタイプもおすすめです。
また、長時間の使用になる場合は、途中で位置を少し調整したり、下に薄手のキャップインナーを使ってクッション性を持たせると、負担を軽減できます。
痛みを我慢せず、自分に合ったフィット感を大切にして選びましょう。
SNS・レビューで話題の商品&リアルな口コミ
実際の使用者の声は、とても参考になります。
Instagramで見つけた実例投稿
「#ハイライトキャップ」で検索すると、実際に使用した方々の写真や動画がたくさん投稿されています。
仕上がりのイメージだけでなく、キャップの被り方や髪の引き出し方、カラー剤の塗り方など、使い方の流れも確認できる投稿が多く、初心者にとってとても参考になります。
人気の投稿には「初めてでも簡単だった」「自然な仕上がりで満足」といったコメントが付いており、リアルな使用感を知る手がかりになります。
また、使用前後のビフォーアフター写真を比較できる投稿もあり、どのくらい印象が変わるのか視覚的に確認できるのもポイントです。
仕上がりのテイストもさまざまで、ナチュラル系からトレンド感のあるデザインまで幅広くチェックできます。
Amazon・楽天レビューで高評価の商品
「初心者でも使えた」「髪が傷まなかった」「説明書がわかりやすかった」などの声が多数寄せられています。
レビュー評価が4.5以上の製品は、実際の購入者からの満足度も高く、安心して選べる目安になります。
レビューでは、カラー剤との相性やキャップの素材感、サイズのフィット感など、公式ページには書かれていないリアルな情報も確認できます。
また、写真付きレビューを見れば実際の使用感や仕上がりもわかりやすく、購入の際の参考になります。
期間限定でポイント還元や送料無料になることもあるため、セール時期を狙って購入するのもおすすめです。
美容師が紹介するYouTube動画も参考に
プロの美容師さんが実際に使っている様子を解説付きで紹介している動画は、初心者にとって大きな助けになります。
動画では、キャップのかぶり方から毛束の引き出し方、カラー剤の塗布テクニックまで一連の流れを確認できるため、事前に見ておくと作業のイメージがしやすくなります。
また、プロならではのちょっとしたコツや失敗しがちなポイントも教えてくれるので、トラブルを防ぐためにも一見の価値ありです。
人気のあるチャンネルでは、セルフカラー初心者向けの解説や、おすすめ商品の紹介、比較レビューなども多数掲載されており、安心して選べるヒントが詰まっています。
まとめ|ハイライトキャップでセルフカラーをもっと楽しもう
ハイライトキャップは、初心者でも手軽にサロン風のカラーを楽しめる便利なアイテムです。
自分に合ったタイプを選び、少しずつ慣れていけば、セルフカラーもきっと楽しくなります。
忙しい日常の中でも、ちょっとしたおしゃれを取り入れて、気分をリフレッシュしてみてくださいね。