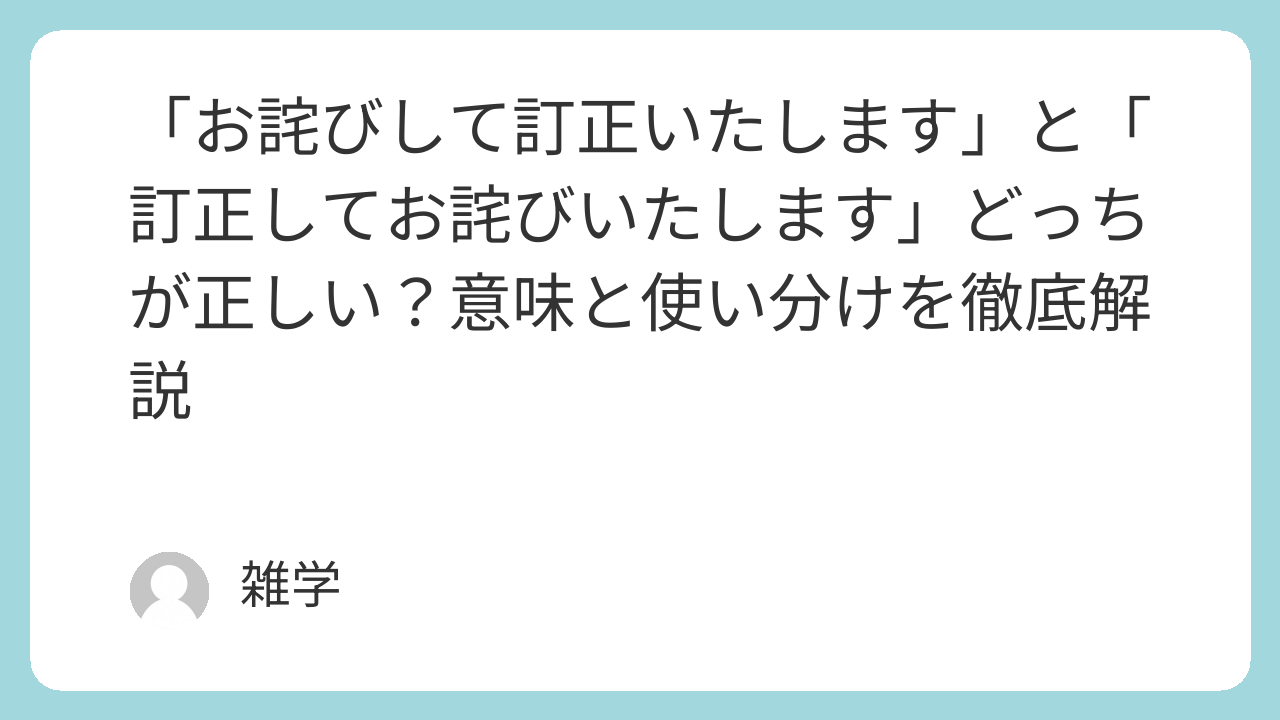仕事のメールやお知らせ文でよく使われる「お詫びして訂正いたします」や「訂正してお詫びいたします」。
一見どちらも同じように見えますが、実は言葉の順序によって伝わる印象や丁寧さが微妙に異なります。
本記事では、2つの表現の違いや正しい使い方を、実際のビジネスメール例文とともにわかりやすく解説。
さらに、言い換え表現や謝罪メールでのマナー、信頼を守るためのポイントも紹介します。
誤った敬語を使ってしまう前に、この記事で正しい言葉選びをマスターしましょう。
「お詫びして訂正いたします」「訂正してお詫びいたします」はどちらが正しい?

まず最初に結論からお伝えすると、どちらの表現も間違いではありません。
ただし、言葉の順番によって相手に伝わる印象や重点が変わるため、使い分けが大切になります。
両方正しいがニュアンスが異なる理由
「お詫びして訂正いたします」及び「訂正してお詫びいたします」は、どちらも謝罪と訂正を含む丁寧な日本語表現です。
しかし、語順が違うことで、どちらの行為を先に重視しているかが変わります。
「訂正してお詫びいたします」は、まず誤りを正してから謝罪する流れを表します。
事実を整理してから謝る形になるため、ビジネスでは最も一般的な表現といえます。
一方で、「お詫びして訂正いたします」については、謝罪の気持ちを先に伝えることで、感情面での誠意をより強く表現する言い方です。
たとえば、お客様や取引先など、相手への配慮を特に重視する場面ではこちらが向いています。
| 表現 | ニュアンス | 主な使用シーン |
|---|---|---|
| 訂正してお詫びいたします | 事実を訂正した上で謝罪 | 報告書・ビジネスメール |
| お詫びして訂正いたします | まず謝罪の気持ちを伝える | 顧客対応・公式発表 |
どんな場面でどちらを使うべきかの判断基準
では、実際のビジネス現場ではどちらを選べば良いのでしょうか。
判断のポイントは「事実関係を重視するか」「感情の伝達を重視するか」です。
もし数字の誤りや資料のミスなど、客観的な情報を訂正する場合は「訂正してお詫びいたします」が自然です。
一方で、相手に不快感を与えてしまったり、迷惑をかけてしまった場合は「お詫びして訂正いたします」と先に謝意を示す方が誠実に感じられます。
つまり、どちらを使うかは“誤りの性質”によって変えるのが最適解なのです。
| 状況 | 推奨される表現 |
|---|---|
| 数字やデータなどの客観的誤り | 訂正してお詫びいたします |
| 相手の感情に影響する誤り | お詫びして訂正いたします |
このように、言葉の順序には「伝える順序の意味」があります。
どちらか一方が正しいというよりも、状況に応じて最も丁寧に聞こえる方を選ぶことが、信頼を得る第一歩です。
ビジネスシーンでの正しい使い分け方

ビジネスの場では、「お詫びして訂正いたします」、「訂正してお詫びいたします」をどのように使い分けるかが重要です。
この章では、文書・メール・会話など、それぞれの場面での自然な使い方を具体的に紹介します。
社外文書・メールでの使い方
まず、取引先や顧客に送る文書やメールの場合は、「訂正してお詫び申し上げます」が最も適しています。
この表現は、誤りを訂正してから謝罪する流れで、ビジネス文書としての整合性が高いのが特徴です。
特に、金額・日程・仕様などの具体的なデータ修正を伝える場合に使われます。
| 場面 | 使える表現 | ポイント |
|---|---|---|
| 金額・数量などの誤り | 訂正してお詫び申し上げます | 客観的な誤りの訂正に適する |
| 納期・スケジュールの変更 | お詫びして訂正いたします | 相手の都合に影響する場合に有効 |
たとえば、以下のような文面が自然です。
「先日お送りした見積書に誤りがございました。正しくは88,000円でしたところ、99,000円と記載しておりました。訂正してお詫び申し上げます。」
このように、事実を明確にし、謝罪の気持ちを添えるのがビジネスでの基本的なマナーです。
会話・電話対応での自然な言い回し
口頭での謝罪では、文章ほど硬くしすぎず、自然に伝わる言葉を選ぶことが大切です。
たとえば、「先ほどのご案内に誤りがございました。正しくは〜です。お詫びして訂正いたします。」というように、流れの中で丁寧に訂正を伝えましょう。
電話対応では「お詫びして訂正いたします」が自然に聞こえるため、柔らかい印象を与えることができます。
| 場面 | おすすめ表現 | 理由 |
|---|---|---|
| 電話での対応 | お詫びして訂正いたします | 相手の気持ちに配慮できる |
| 報告・説明の途中で誤りを訂正 | 訂正してお詫び申し上げます | 冷静で誠実な印象を与える |
言葉遣いのポイントは、謝罪を丁寧にしつつも、簡潔で聞き取りやすい表現を選ぶことです。
社内でのカジュアルな訂正表現
社内メールや同僚への連絡など、フォーマルさをそこまで求めない場合は、少し柔らかい言い回しが適しています。
たとえば、「先ほどの資料に誤りがありました。修正しましたのでご確認ください。申し訳ありません。」というように、平易な言葉で伝えると良いでしょう。
状況によっては「訂正の上、お詫びいたします」や「誤りがありましたので修正いたしました」でも問題ありません。
| 相手 | 適切な表現 | フォーマル度 |
|---|---|---|
| 上司・他部署 | 訂正の上、お詫び申し上げます | ややフォーマル |
| 同僚・チーム内 | 修正しました。申し訳ありません。 | カジュアル |
ビジネスでは「誰に対して」「どんな目的で」謝るのかを意識することで、最適な言葉遣いが選べるという点を覚えておきましょう。
「訂正とお詫び」の実践例文集【シーン別】
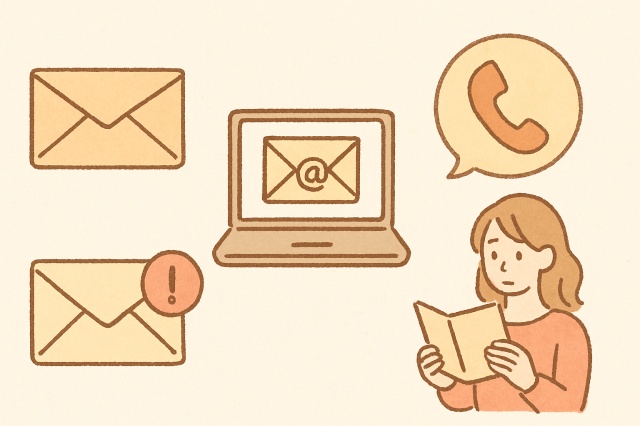
ここでは、実際のビジネスシーンで「訂正とお詫び」をどのように使うかを具体的に見ていきましょう。
状況ごとに使える例文を紹介しますので、そのまま使えるテンプレートとしても活用できます。
書類・資料の誤記を訂正する場合
数字や文言の間違いなど、資料の誤記は多いミスの一つです。
この場合は、訂正内容を明確に示し、正しい情報を添えることがポイントです。
| 状況 | 例文 |
|---|---|
| 見積書の金額誤り | 「先日お送りした見積書に誤りがございました。正しくは49,800円でしたところ、48,9000円と記載しておりました。訂正してお詫び申し上げます。」 |
| 資料内のデータ誤記 | 「ご案内資料の一部に誤りがありました。正しい数値は以下の通りです。お詫びして訂正いたします。」 |
数字のような客観的なデータの訂正では、「訂正してお詫び申し上げます」を使うとフォーマルで誠実な印象を与えます。
案内・日程の誤りを訂正する場合
イベントや会議などの日程に関する誤りは、相手の予定に直接影響を与えるため、より丁寧な表現が求められます。
| 状況 | 例文 |
|---|---|
| 会議日程の誤り | 「会議の開催日時について誤った情報をお伝えしてしまいました。正しくは10月15日(火)15時から開始でございます。お詫びして訂正させていただきます。」 |
| セミナーの案内ミス | 「セミナーご案内メールにて、日付に誤りがございました。正しい開催日は○月○日でございます。訂正の上、深くお詫び申し上げます。」 |
このようなケースでは、まず正しい情報を示し、次に謝罪する流れが自然です。
「お詫びして訂正いたします」は、相手の不便に配慮した柔らかい印象を与えるため、顧客対応などに特に適しています。
メール送信ミスを訂正する場合
ビジネスメールでは、宛先ミスや添付ファイルの誤りなどもよくあるトラブルです。
この場合は、誤りの内容を明示し、正しいデータを再送することが重要です。
| 状況 | 例文 |
|---|---|
| 添付資料の誤り | 「お送りしたメールに添付いたしました資料の内容に一部誤りがございました。正しい資料を改めてお送りいたします。訂正の上、深くお詫び申し上げます。」 |
| 誤送信メール | 「誤って別の宛先へメールを送信してしまいました。大変申し訳ございません。先のメールは破棄していただけますでしょうか。訂正してお詫び申し上げます。」 |
このような場合、単に「訂正します」だけでなく、再送や確認依頼を明記することが信頼を保つポイントになります。
「訂正してお詫びいたします」の言い換え・類語表現
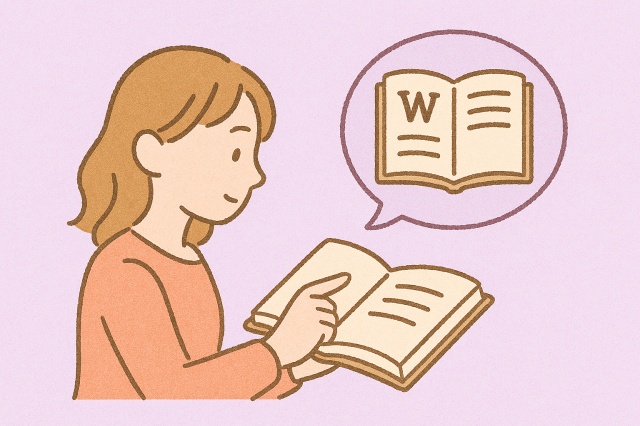
「訂正してお詫びいたします」は、ビジネスでよく使われる丁寧な謝罪表現ですが、状況によっては別の言い回しを選んだ方が自然な場合もあります。
ここでは、目的や相手に応じた言い換え表現を紹介します。
より丁寧に伝えたいときの表現
重要な取引先や上司に対しては、より丁寧な謝罪を示す必要があります。
その場合は、次のような表現が適しています。
| 言い換え表現 | 使用例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 誤りを訂正し、深くお詫び申し上げます | 「先日のご案内に誤りがございました。誤りを訂正し、深くお詫び申し上げます。」 | 「深く」を加えることで謝罪の気持ちが強調される |
| 誤記を修正し、謹んでお詫び申し上げます | 「報告書内の数値に誤りがありました。誤記を修正し、謹んでお詫び申し上げます。」 | 「謹んで」によりフォーマルさが増す |
「深く」や「謹んで」を加えると、誠実で重みのある印象になるため、フォーマルな謝罪文に適しています。
カジュアルな職場で使える表現
社内の同僚やチームメンバーなど、関係が近い相手には、少し柔らかい表現を選ぶと良いでしょう。
| 言い換え表現 | 使用例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 訂正の上、お詫びいたします | 「昨日の報告内容に誤りがありました。訂正の上、お詫びいたします。」 | 短く簡潔で、社内連絡に適する |
| 誤りがありましたので、修正いたしました | 「資料内に誤りがありましたので、修正いたしました。申し訳ありません。」 | カジュアルで、迅速な印象を与える |
特にSlackやTeamsなどのビジネスチャットでは、形式張った謝罪よりも、簡潔で誠意のある一言が信頼を生むこともあります。
公的文書・公式発表で使うフォーマル表現
ニュースリリースや報告書、社告(しゃこく)などの公式文書では、格式のある言葉遣いが求められます。
この場合は、次のような表現を使用します。
| 言い換え表現 | 使用例 | 特徴 |
|---|---|---|
| 誤った記載を修正し、深くお詫び申し上げます | 「当社ホームページ上の表記に誤りがございました。誤った記載を修正し、深くお詫び申し上げます。」 | 企業の公式発表や報告書に多く使われる |
| 誤記を訂正し、関係各位にお詫び申し上げます | 「商品仕様書の内容に誤りがございました。誤記を訂正し、関係各位にお詫び申し上げます。」 | 幅広い相手に向けた丁寧な謝罪に適する |
公式発表では、個人ではなく企業全体の姿勢が問われるため、「深く」「関係各位」といった言葉を使うと誠実さと責任感を伝えることができます。
TPOに合わせた言葉選びが、相手の信頼を守るための重要なポイントです。
謝罪・訂正メールで信頼を守る5つのポイント
謝罪や訂正のメールを送るとき、ただ「申し訳ありません」と伝えるだけでは信頼を保つことはできません。
ここでは、相手に誠意が伝わり、関係を良好に保つための5つの基本ポイントを解説します。
迅速な対応の重要性
誤りに気づいたら、できるだけ早く対応することが第一です。
スピードは誠意を示す最も分かりやすい手段です。
特にビジネスでは、対応の遅れが信用の低下につながることもあります。
「誤りに気づいたらすぐ訂正」が鉄則と覚えておきましょう。
| 対応の早さ | 印象 |
|---|---|
| 即日対応 | 誠実・信頼できる印象 |
| 翌日以降の対応 | やや印象が下がる |
| 数日放置 | 信頼を損なう可能性が高い |
具体的な誤り内容の明示
「何がどう間違っていたのか」を明確に説明することも大切です。
あいまいな表現では、相手が混乱したり、不信感を抱くことがあります。
たとえば「価格を30,000円と記載すべきところ、3,000円と誤っておりました。」のように具体的に伝えるのが望ましいです。
言い訳を避ける誠実な文面
誤りの理由を説明する際、言い訳がましくならないよう注意しましょう。
「システムの不具合で」「担当者の確認漏れで」といった表現を多用すると、責任逃れの印象を与えることがあります。
必要であれば経緯を簡潔に述べた上で、謝罪を中心に据える構成が信頼を損なわないコツです。
| 悪い例 | 良い例 |
|---|---|
| 「システムの不具合で誤った情報をお送りしました。」 | 「誤った情報をお送りしてしまいました。確認が不十分でした。訂正してお詫び申し上げます。」 |
再発防止策を添える方法
同じミスを繰り返さないという姿勢を示すと、相手の信頼を取り戻しやすくなります。
「今後はダブルチェック体制を導入いたします」など、具体的な対策を一文添えるのがおすすめです。
これは単なる形式ではなく、「誠意の可視化」として大きな効果を持ちます。
| 誠意が伝わる再発防止の一言 |
|---|
| 今後は送付前に二重チェックを行い、再発防止に努めます。 |
| 確認プロセスを見直し、同様の誤りが起きないよう改善いたします。 |
件名とフォローアップのコツ
メールを開いてもらうためには、件名も重要な要素です。
「【重要】訂正とお詫び」「【訂正】○○に関するご案内」など、一目で内容が伝わる件名にしましょう。
また、訂正後に「ご確認いただけましたでしょうか」とフォローすることで、より丁寧な印象を与えられます。
「早さ+具体性+フォロー」の3要素が、信頼を守る鍵になります。
まとめ|状況に応じた言葉選びで誠意を伝えよう
ここまで、「お詫びして訂正いたします」「訂正してお詫びいたします」の違いや使い方を解説してきました。
結論として、どちらも正しい表現ですが、使い分けのポイントを押さえることでより誠実な印象を与えることができます。
| 表現 | 特徴 | 主な使いどころ |
|---|---|---|
| 訂正してお詫びいたします | 事実を訂正してから謝罪する | ビジネス文書・報告書・公式連絡 |
| お詫びして訂正いたします | 謝罪の気持ちを先に伝える | 顧客対応・感情的配慮が必要な場面 |
ビジネスの現場では、一般的に「訂正してお詫び申し上げます」が多く使われます。
一方で、相手の気持ちを重視したい場面では「お詫びして訂正いたします」が自然です。
状況に合わせて言葉を選ぶことが、誠意を伝える第一歩になります。
また、謝罪メールや訂正連絡では、スピードと具体性がとても大切です。
誤りを放置せず、すぐに訂正を行い、何が間違っていたのかを明確に説明しましょう。
そして、再発防止策を添えることで、信頼を損なわずに問題を解決できます。
最後に、謝罪の言葉は「マナー」ではなく「信頼の証」です。
誠実な対応は、ミスをきっかけに信頼を深めるチャンスにもなることを忘れないようにしましょう。
適切な表現と丁寧な対応で、ビジネスコミュニケーションをより円滑にしていきましょう。