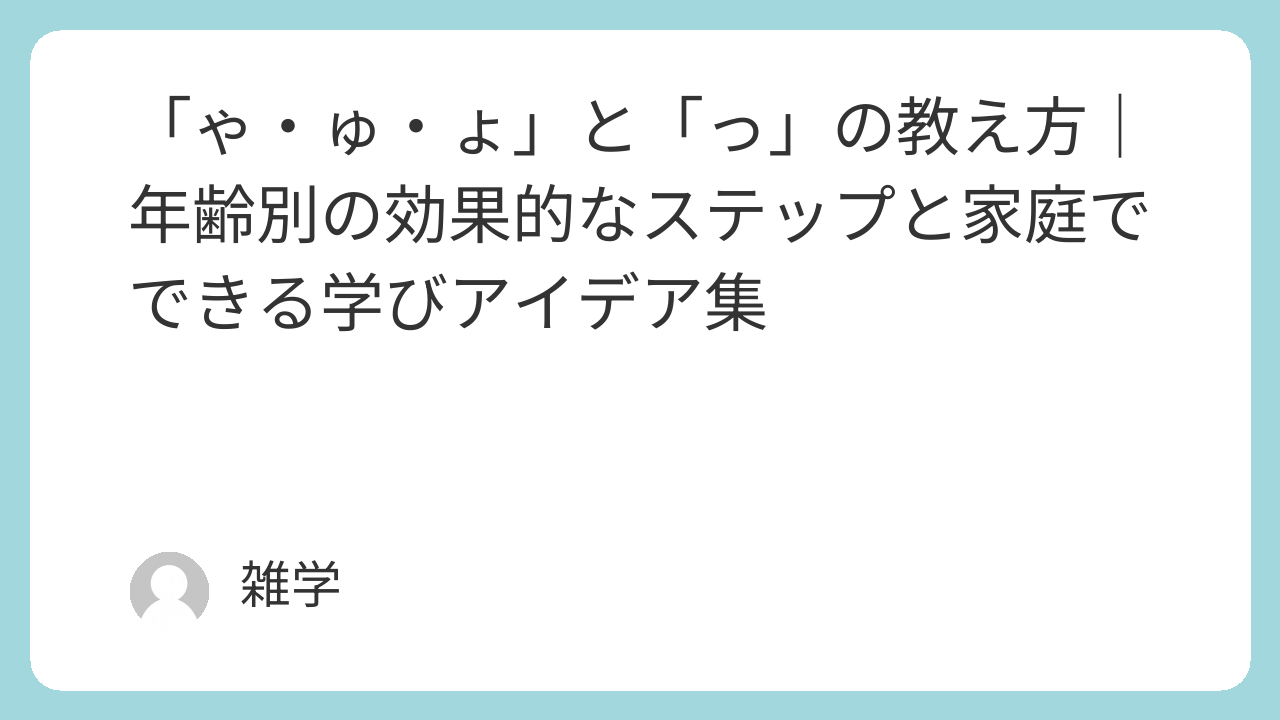お子さんがひらがなを覚え始めたとき、「ゃ・ゅ・ょ」や「っ」のような小さい文字でつまずくことって、意外と多いですよね。
これらの文字は、見た目が普通のひらがなよりも小さくて、発音も少し独特なため、最初はなかなかうまく理解できなかったり、言い間違えたりしてしまうものです。
特に拗音や促音は、音のリズムや区切り方が普段の会話と違うため、耳で聞いても区別しづらかったり、文字にする際に混乱してしまうことがあります。
でも、安心してください。
無理に詰め込もうとせず、おうちでの遊びや日常のやりとりの中に少しずつ取り入れていくことで、自然と身についていきます。
親子で一緒に楽しみながら、「できた!」という成功体験を積み重ねていくことが、何より大切なポイントです。
この記事では、拗音(ゃ・ゅ・ょ)と促音(っ)を子どもにわかりやすく教えるための年齢別のステップや、日常生活の中で楽しく取り入れられるアイデアをご紹介していきます。
はじめて取り組む方でも安心して読める内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください
「ゃ・ゅ・ょ」と「っ」の違いをわかりやすく解説
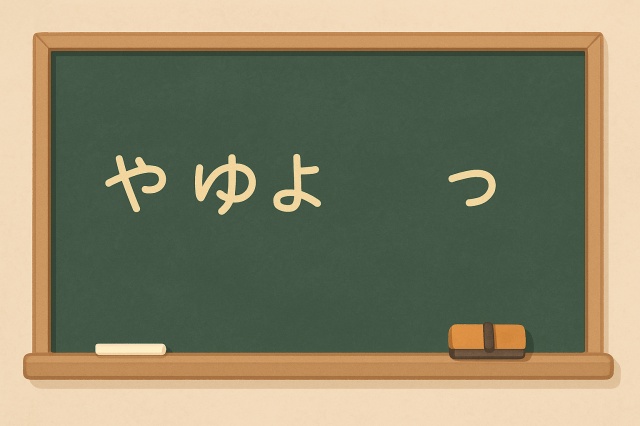
「ゃ・ゅ・ょ」は、前の文字とくっついて「きゃ」「しゅ」などのように読む拗音(ようおん)です。
「っ」は、音を一度止めてから出す促音(そくおん)で、「がっこう」「きって」などに使われます。
どちらも音に変化があるため、耳で聞いて理解する力がポイントになります。
間違いやすい例としては、「きよう(今日)」と「きょー(拗音)」の違いなどがあります。
このように、音の違いを体感することが理解への第一歩になります。
年齢別に見る「ゃ・ゅ・ょ」の教え方|段階的に進めるコツ

3〜4歳:まずは音のリズムを楽しむ遊びを
この時期は、学ばせようとするよりも、音に親しみながら自然に覚えていけるような関わりがとても大切です。
まずは「聞く・まねる」ことに集中して、生活の中でリズムよく繰り返す言葉をたくさん取り入れていきましょう。
例えば、「きゃっ」「しゅっ」といった拗音を、ジャンプや手たたきなどの動作と組み合わせて遊ぶと、お子さんは楽しみながら音を体感できます。
「きゃー!おばけ!」などとごっこ遊びの中に自然に取り入れるのもおすすめです。
また、「じゃんけんぽん!しょ!」のような遊びに「しゅっ」「ちゃっ」などの音を混ぜたり、「くしゃみごっこ」で「はっくしゅん!」と言ってみたりすると、笑いながら覚えられます。
こうした繰り返しが、無理なく学びにつながる土台になります。
4〜5歳:似ている音の違いを感じる聞き分け練習
この年齢になると、音の違いを少しずつ意識できるようになってきます。
「きゃ」と「きや」、「しゅ」と「しゆ」など、似ている音を聞き比べることで、音の構造への理解が深まります。
カードや絵を使って「どっちの言葉かな?」とクイズ形式にしたり、
「しゅーくりーむ」と「しゆーくりーむ」など、実際に口に出して違いを感じる練習をしてみましょう。
また、親子で声を出しながらまねっこゲームをしたり、「音探しごっこ」をして遊ぶことで、楽しみながら正しい音に触れることができます。
5〜6歳:言葉と文字のつながりを意識した練習へ
音と文字のつながりに気づき始めるこの時期は、学びのステップアップにぴったりです。
まずは、拗音が出てくる簡単な絵本を一緒に読みながら、「この言葉には『きゃ』があるね」と気づかせてあげましょう。
自分で声に出して読むことで、音と文字が結びついていきます。
さらに、ひらがなの練習ノートなどで「きゃ」「しゅ」「ちょ」などの文字を書いてみたり、身近な単語を一緒に書いてみるのも効果的です。
楽しみながら繰り返すことで、読む・書く・話す力がバランスよく育っていきます。
年齢別に見る「っ(小さいつ)」の教え方|つまずかない段階アプローチ

3〜4歳:「つまる音」を体感するまねっこ遊び
「がっこう」や「きって」のように、一度音が止まる「っ」は、言葉のリズムやテンポに大きな違いをもたらします。
この年齢では、まだ文字としての理解は難しいかもしれませんが、体を使って「音のつまる感じ」を体感させることで、自然と身につけることができます。
例えば、「ジャンプ!」の前に「っ」で一拍おくと、「ジャ…ンプ!」といったリズムになり、音の止まり方がわかりやすくなります。
また、「ストップゲーム」や「ピタッと止まるゲーム」などの遊びを取り入れて、動きと言葉を結びつけるのも効果的です。
ジャンケンの掛け声を「じゃっ、けっ、ん、ぽん!」とアレンジして遊んでみるのも楽しい方法ですよ。
4〜5歳:リズムやテンポの違いを感じるゲーム
「がこう」と「がっこう」の違いを意識できるようになってきたら、言葉のリズムやテンポに注目するゲームを取り入れてみましょう。
例えば、「早口ことばごっこ」で、促音の入った言葉をテンポよく言ったり、
親がわざと「がこう」と「がっこう」を言い分けて、「どっちが正しいかな?」と当てっこするのもおすすめです。
「たっぷり」と「たぷり」のように、意味が変わる言葉を比べることで、自然と正しい発音に気づけるようになります。
リズムに合わせて手をたたく・ジャンプするなど、体を動かしながらの音遊びをするとより効果的です。
5〜6歳:「書く・読む・話す」のバランスを取った学習法
この時期になると、「っ」を含む言葉の意味や使い方に興味を持ち始めます。
まずは一緒に「っ」が入った言葉を読んでみましょう。
「はっぱ」「けっこん」「チケット」「ラーメン」など、身近でよく目にする言葉を選ぶと、学びにつながりやすくなります。
そのあとに、ひらがなの練習帳などを使って、「っ」の書き方にも取り組んでみましょう。
「大きな『つ』じゃないよ、小さい『っ』なんだよ」と声をかけてあげると、違いを意識できます。
さらに、簡単な文章の中に「っ」を使った単語を入れて読んでみることで、読む力・書く力・話す力のバランスを整えられます。
遊びの中に取り入れながら、少しずつステップアップしていきましょう。
拗音・促音を遊びながら学べる!家庭でできる言葉あそびアイデア

お買い物やおでかけを活かした「音あそび」
お買い物のときに「しゅーくりーむ」「きゃべつ」「ちゅうかそば」など、拗音が含まれる商品名を親子で一緒に探してみましょう。
「これは『きゃ』が入ってるね」「『しゅ』ってどこにあるかな?」と声をかけることで、自然と耳と目で音に気づけるようになります。
また、スーパーでの時間を利用して「拗音探しゲーム」や「お名前クイズ」などのアレンジも楽しいです。
信号待ちでは、「がっこう」「きっぷ」「カップ」など、促音の入った言葉でしりとりをしたり、「『っ』が入ってる言葉、言えるかな?」とクイズ形式で遊ぶのもおすすめです。
通園・通学の道中など、日常のちょっとした時間に楽しめる工夫を取り入れると、学びの幅がぐんと広がります。
お風呂・食事の時間を使った“ながら学習”
夕食の時間には「今日のごはんに『っ』がつく食べ物あるかな?」と問いかけてみたり、「きゃべつ」「しゃけ」「にっこり」などの音が入った食材を話題にするのも効果的です。
また、お風呂の中では「きゃ」「しゅ」「ちょ」などの音を使った“あいうえお”ごっこをしてみましょう。
「『しゅ』から始まる言葉なにがある?」とクイズを出したり、湯気に文字をなぞる遊びを取り入れることで、視覚と触覚も一緒に刺激できます。
普段の会話に少しだけ意識をプラスするだけで、楽しい学びの時間に早変わりしますよ。
毎日続けるためのちょっとした工夫
学びは毎日の積み重ねがとても大切ですが、負担になってしまうと続きません。
だからこそ、一日5分程度の「遊びの中での音あそび」がおすすめです。
カレンダーにシールを貼って「毎日できたね」を見える化したり、お子さんの好きなキャラクターの真似をしながら「きゃ」「しゅ」を発音して遊ぶのも効果的。
「昨日は『がっこう』が言えたね!今日は『しゅーくりーむ』に挑戦しようか」など、ポジティブな声かけを続けることで、お子さんのやる気がぐんと伸びていきます。
たくさん褒めて、「できたね!」「がんばったね!」という成功体験を積み重ねていきましょう。
遊び感覚で学べる!おすすめ家庭学習ツール・教材

シール・カード・絵本などのアナログ教材
拗音や促音が出てくる絵本は、お子さんの耳と目に同時に働きかけてくれるので、学習の入り口にぴったりです。
たとえば、「しゅっしゅぽっぽ」「きゃべつちゃん」など、音の響きが楽しい絵本を一緒に読むことで、自然と耳に残りやすくなります。
文字カードや音カードは、神経衰弱や神経衰弱風のゲームにアレンジして遊ぶことで、楽しみながら文字と音の組み合わせを覚えられます。
また、シール貼りやぬりえも、指先を使いながら言葉に親しむ絶好の機会。
「『しゅ』の絵にシールを貼ってみよう」「『っ』がつく言葉を塗ってみよう」といった遊びで、音の感覚を定着させていきましょう。
アプリ・動画・音声付き絵本などのデジタル教材
近年は、スマホやタブレットを活用した知育アプリや音声付き絵本も豊富にあります。
音と文字が同時に表示されたり、タッチすると音声が流れるアプリを使えば、視覚と聴覚を同時に刺激できます。
特に拗音や促音は耳で聞くことが大切なので、正しい音声でくり返し聞けるデジタル教材は非常に有効です。
YouTubeの知育チャンネルでは、短いアニメや歌を通して「きゃ・しゅ・ちょ」などの音を楽しく学べます。
使う時間や内容を親が管理しながら、親子で一緒に楽しむのがおすすめです。
おすすめ教材リンク・口コミのあるものも紹介
「NHK for School」では、ひらがなや音の学びに関する動画や教材がそろっていて、無料で使えるのも嬉しいポイントです。
また、「ことばのえほん」シリーズや「くもんのひらがなカード」などは、親御さんたちからの評判も高く、安心して使える教材です。
口コミを確認しながら、お子さんの興味に合うものを選ぶと、より効果的に学びが進みます。
図書館や児童館に試せる教材が置いてある場合もあるので、実物を手に取って選ぶのもよいでしょう。
「ゃ・ゅ・ょ」「っ」が苦手な子へのフォロー方法

-
正しく言えないからといって叱らないこと。まずは「がんばって言おうとしている気持ち」を受け止めてあげることが大切です。
-
できたときには、小さなことでもしっかり褒めてあげること。「今の『きゃ』、きれいに言えたね」「『がっこう』って言えてすごい!」と具体的に声をかけると、子どもは自信を持ちやすくなります。
-
完璧に言えなくても、「伝わったね」「わかってくれたね」「気持ちが届いたよ」など、気持ちを受け止める声かけが大切です。
-
他の子と比べないように心がけてください。それぞれの子に合ったペースがあり、ゆっくり成長していくのも素晴らしいことです。
-
絵本を読むときや会話の中で、あえて拗音・促音を多く含んだ言葉を使って聞かせるのもよい方法です。「今日のおやつは“しゅーくりーむ”だよ」「“きって”を貼ろうね」など、自然なやり取りの中で、少しずつ慣れていけます。
お子さんのペースを尊重しながら、できることを少しずつ増やしていくことが何よりも大切です。
焦らず、優しい気持ちで寄り添ってあげてくださいね。
保育園・幼稚園・小学校前にやっておきたい準備

入園・入学を控える時期には、「読む」「聞く」「話す」の3つの力をバランスよく伸ばしておくことが、これからの学びに向けた大切な準備になります。
特に文字に対する興味を持ち始めるこのタイミングでは、机に向かう学習よりも、日常生活の中で自然に言葉に触れる時間を意識して作るのがポイントです。
たとえば、絵本の読み聞かせでは拗音や促音が出てくる場面で声の調子を変えて読んだり、お子さんと一緒に言葉のリズムを楽しんだりすることで、言葉への関心が育ちます。
また、日常会話の中で「これって『しゅ』がついてるね」「『っ』があるときは音が止まるよね」と軽く声をかけてあげるだけでも、拗音・促音への理解が少しずつ進みます。
園や学校で先生のお話を聞く力や、お友達とのやりとりに必要な表現力を養うためにも、おうちでの声かけや会話の積み重ねが大切です。
もちろん、「拗音・促音が完璧じゃないとだめ」ということはありません。
大切なのは、言葉に親しみながら「ことばって面白い!」と感じてもらうこと。
無理なく、楽しく、親子で一緒に学んでいく姿勢を大切にしていきましょう。
無料で使える!拗音・促音に役立つ外部学習コンテンツ紹介

-
NHK for School:拗音や促音の使い方を含む言語教育に関する番組が豊富にそろっており、動画やクイズを通して楽しく学べます。アニメ形式で展開されるので、小さなお子さんでも飽きずに集中できます。
-
YouTube知育チャンネル:親子で一緒に見られる動画がたくさんあります。「ひらがなの歌」や「ことば遊びシリーズ」など、歌やリズムにのせて覚える工夫がされており、遊び感覚で言葉に親しめます。コメント欄や再生リストで他の関連動画を探すのもおすすめです。
-
無料プリントサイト(例:「ちびむすドリル」など):文字練習や迷路、言葉探しプリントなど、紙で学びたいご家庭にぴったりです。拗音・促音に特化したページもあり、繰り返し練習できるのがポイント。印刷して冷蔵庫や机に貼って、いつでも使えるようにしておくと便利です。
-
教育系アプリ(例:「こどもえいごずかん」「もじぴったん」など):音声付きで「きゃ・しゅ・ちょ」などを繰り返し聞いて発音したり、文字をなぞって形を覚えたりできるアプリが多数あります。インタラクティブな仕組みで、お子さんが自分で操作しながら楽しめるのも魅力です。ゲーム感覚で進められるので、集中力が続きにくい子にもおすすめです。
これらのツールはすべて無料で利用できるものばかりなので、気軽に試して、お子さんに合ったスタイルを見つけてみてください。
まとめ|焦らず、子どもの「できた!」を育てることがいちばん大切
拗音・促音は、すぐに覚えるものではありません。
でも、親子で楽しみながら少しずつ触れていくことで、自然に身についていきます。
「うまくできない」よりも、「今日はこれができたね」を大切に。
毎日のちょっとした言葉あそびが、子どもの言葉の力を育ててくれます。