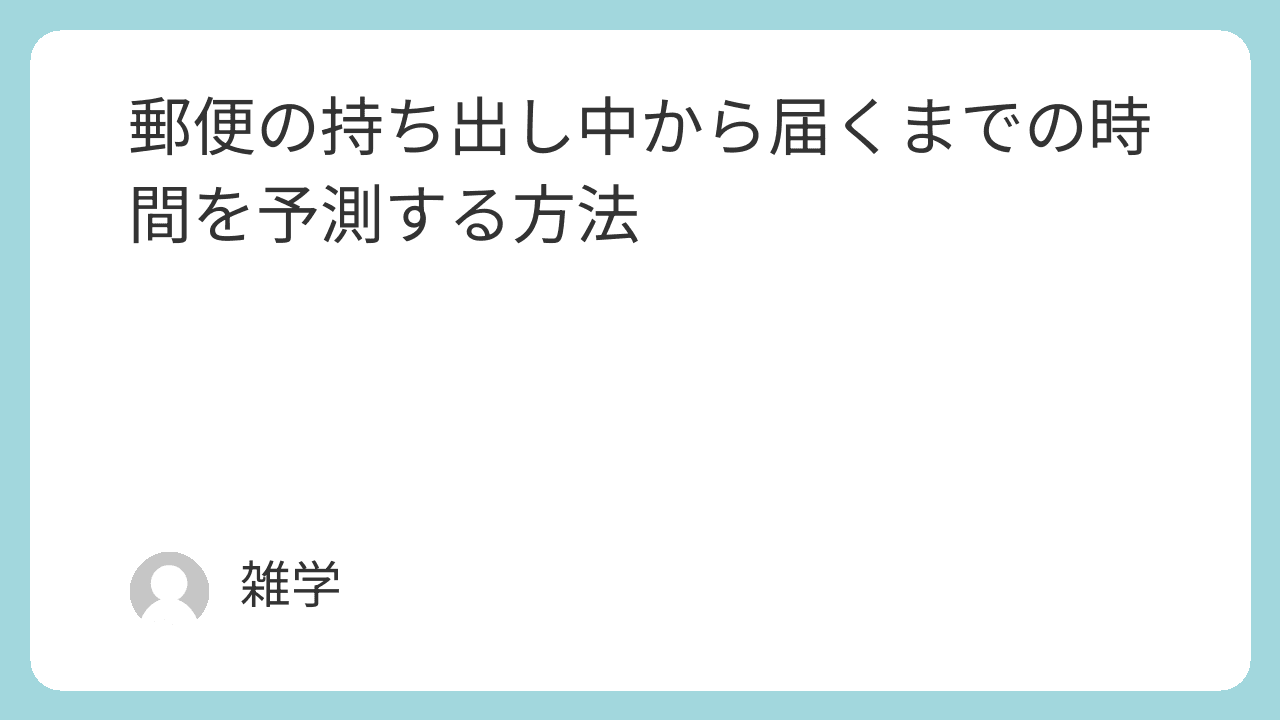郵便物の追跡サービスで「持ち出し中」と表示されると、「あとどれくらいで届くのか?」と気になる方も多いと思います。
この記事では、郵便が持ち出し中になってから実際に届くまでの流れや、到着時間を予測するためのポイントを詳しく解説します。
また、配達状況の確認方法や遅延があった場合の対応策についても紹介します。
郵便の持ち出し中から届くまでの予測方法

郵便が持ち出し中の状況とは
郵便局から配達担当者が郵便物を持って外に出た状態を「持ち出し中」といいます。
このステータスが表示されるのは、郵便物がすでに配達ルートに乗っており、最終的な配達先に向かって移動していることを意味します。
配達ルートや地域によって順番は異なりますが、基本的にはその日のうちに配達される可能性が高い状態です。
郵便局からの持ち出し中の荷物の流れ
郵便物は最寄りの集配局で仕分けされた後、配達エリアを担当する配達員に振り分けられます。 配達員はバイク、自転車、軽自動車などの専用車両に郵便物を積み込み、効率的なルートをもとに配達を開始します。
この際、配達員の経験や地域の地理状況によって、ルートや配達順が調整されることもあります。
また、配達中の荷物は通常の郵便物だけでなく、書留や速達などの特別な郵便物も含まれているため、それぞれ優先度に応じて配達順が決まります。
持ち出し中から届くまでの時間を知るメリット
配達中であることが分かれば、荷物の到着が近いことを予測できます。
これにより、自宅での受け取り準備を整えたり、外出のタイミングを調整することが可能になります。
特に、書留や本人確認が必要な荷物などは、確実に在宅して受け取る必要があるため、到着予測が非常に役立ちます。
また、持ち出しから一定時間経っても届かない場合は、配達状況に問題がある可能性もあるため、早めに対応するための判断材料にもなります。
配達状況の確認と追跡方法

追跡番号を使った配達状況の把握
日本郵便の追跡サービスでは、送り状に記載された追跡番号を入力することで、郵便物がどの地点にあるのか、どの段階まで進んでいるのかを把握することができます。
追跡番号は郵便物ごとに固有で、配達状況が更新されるたびに反映されるため、荷物の現在地をリアルタイムで確認する手がかりになります。
特にビジネス用途や重要書類の受け取りなどでは、この情報を基にスケジュール調整を行うことができ、非常に便利です。
公式サイトやアプリでの配達状況確認
パソコンを使ってブラウザから日本郵便の公式サイトにアクセスするか、スマートフォンの専用アプリを利用することで、手軽に配達状況を確認できます。
アプリでは通知機能を設定することで、ステータスが更新された際にプッシュ通知を受け取ることも可能です。
これにより、持ち出しや配達完了のタイミングをすぐに把握できるため、荷物を確実に受け取るための準備がしやすくなります。
また、同一のアカウントで複数の荷物を管理することもできるため、家族の分もまとめて確認できます。
持ち出し中の郵便物が届くまでの時間

通常の配達時間と遅延要因
通常、郵便物の配達は午前中から午後の早い時間帯に集中して行われることが多く、特に平日はこの傾向が顕著です。
ただし、配達エリアや郵便局の処理状況によっては、午後遅くにずれ込むことも珍しくありません。 天候の急変(台風、大雪、大雨)や交通事故、道路工事などの影響で、配達が予定より遅れるケースもあります。
また、地域によっては配達員の人数や担当範囲の広さによって、時間のばらつきが発生します。
さらに、郵便物の量が多い時期や特定の曜日には配達のペースが変わることもあり、通常通りの時間帯に届かない場合もあります。
配達時の営業時間と希望時間
郵便局の配達業務は、基本的に平日の午前9時から午後5時前後まで行われています。 この時間帯の中で、希望配達時間を指定している場合には、システム上で優先的に調整されます。
たとえば「午前中」「14時~16時」などの枠が指定でき、受け取りやすい時間に合わせた配達が可能です。
ただし、希望時間帯の配達であっても交通事情や突発的な遅延要因によって時間通りに届かない可能性があるため、時間帯はあくまで目安と捉える必要があります。
地域別の配達時間の違い
都市部と地方では、郵便配達のスケジュールに大きな違いが出ることがあります。 都市部では配達件数が多いため、複数の配達員で分担されることで比較的早い時間帯に届くことが多い傾向にあります。
一方で、山間部や郊外などの地方エリアでは、配達に時間がかかるため、午後遅くの配達になることもあります。
また、道幅の狭さや交通信号の数、坂道の有無など、地域特有の地理的な条件も配達時間に影響します。
同じ「持ち出し中」の表示であっても、これらの条件によって到着時間に差が生じるのは自然なことです。
郵便物が届かない場合の対処法
再配達の依頼方法
不在で受け取れなかった場合は、ポストに投函される不在票に従って再配達の手続きを行うことで、再度郵便物を届けてもらうことができます。
再配達は電話、インターネット、スマートフォンアプリ、そしてQRコードを読み込む方法など、いくつかの手段で申し込むことができます。
申し込み時には、不在票に記載された「お問い合わせ番号(追跡番号)」や配達希望日時を入力または選択する必要があります。
一部地域では、LINEやAIチャットボットを通じて申し込むことも可能になっており、よりスムーズな手続きが期待できます。
再配達の受付時間にも注意が必要で、地域や曜日によっては当日配達ができないこともあるため、なるべく早めに申し込むことが大切です。
不在票の意味と取り扱い
ポストに入っている不在票は、配達時に受取人が不在だったことを知らせる重要な通知です。
不在票には、荷物の種類や追跡番号、再配達の申込方法、連絡先電話番号、配達員の名前や配達日時などが記載されています。
また、不在票には再配達可能な日時帯や、郵便局での保管期限も明記されているため、記載内容をしっかり確認することが大切です。 破棄せずに保管しておけば、万一問い合わせや再配達時に必要な情報をすぐに参照できます。
特に、複数の荷物を管理している場合には、不在票ごとに情報を整理しておくと便利です。
保管中の郵便物の確認方法
再配達を申し込まないまま一定期間(通常は7日間〜10日間)が経過すると、郵便物は一時的に郵便局に保管されます。
この保管期間を過ぎても受け取りがない場合、差出人に返送されてしまうことがあります。
郵便物が保管されているかどうかを確認したいときは、不在票に記載されている郵便局に電話をかける、もしくは直接窓口に訪れて問い合わせることができます。
郵便局では、本人確認書類(免許証など)を提示することで保管中の郵便物を受け取ることが可能です。
また、ゆうびんIDなどを利用したオンラインサービスでも、保管状況の確認や受取方法の選択ができる場合があります。
影響を与える要因と時間帯
天候や交通の影響
大雨や大雪、台風、強風などの悪天候が発生すると、道路状況が悪化し、交通機関の乱れが発生します。 その結果、郵便局からの持ち出しが遅れるだけでなく、配達ルートの見直しや一時中断が行われることがあります。
また、大規模な事故や道路工事が発生した場合も、配達車両が通行できずに遅延が発生します。
天候や交通の影響は、特に地方や山間部などでは大きく、通常よりも配達が1日以上遅れるケースもあります。
そのため、天候情報や道路交通情報を事前に確認しておくと、配達の予測がしやすくなります。
繁忙期の配達状況の変化
年末年始やお中元・お歳暮などの贈答シーズン、さらにバレンタインや母の日などのイベント前後は、郵便物や荷物の量が一気に増加します。
このような時期は、通常の倍以上の荷物を処理しなければならないため、配達にかかる時間も延びがちです。
また、これらの繁忙期には一時的に臨時スタッフが投入されることもありますが、それでも処理能力を超える荷物が集中することがあります。
その結果、通常より1〜2日程度配達が遅れる可能性があります。
このような時期には、なるべく早めに発送したり、余裕を持って到着を待つことが推奨されます。
急ぎの荷物と通常荷物の違い
速達や書留、レターパックプラスなどのサービスを利用した郵便物は、通常の定形郵便物よりも優先的に処理されます。
これらの急ぎ扱いの郵便物は、郵便局内での仕分け時点で優先順位が高く設定されており、配達ルートでも早い段階で配達されることが一般的です。
特に速達は、午前中に差し出せばその日のうちに届く可能性が高く、ビジネス用途でも頻繁に利用されています。
一方、通常郵便はコストが安い反面、配達のスピードでは劣るため、急ぎで荷物を届けたい場合は、優先サービスを活用することが効果的です。
郵便物の到着予定の確認方法
配達予定日の確認方法
追跡サービスを活用することで、郵便物の配達予定日を確認できることがあります。
この予定日は、郵便局側の処理状況や配達スケジュールに基づいて自動的に算出され、画面上に表示されます。
また、差出人が配達日や時間帯を指定した場合には、受取人に対して通知メールが届く設定となっていることもあります。
このメールには、追跡番号や受け取り日時、荷物の内容などが記載されている場合があり、確認しておくと配達に備える際に非常に役立ちます。
午前中と午後の配達の違い
配達時間帯の違いにより、荷物の受け取りやすさに差が生じることがあります。
午前中指定の荷物は基本的に9時から12時の間に配達されることが一般的で、早めに受け取りたい場合に適しています。
一方、午後指定の荷物は12時から17時の間に届けられることが多く、昼以降の在宅時間に合わせた調整がしやすいです。
ただし、配達地域や交通状況、郵便局の運営体制によって、時間帯が多少前後することもあります。
また、希望時間帯の指定があっても、配達が集中している場合にはその時間を過ぎて届くこともあるため、あらかじめ余裕を持って対応することが大切です。
リアルタイムでの配達状況の追跡
郵便物の現在地や進捗状況をリアルタイムで確認できる追跡サービスは、非常に便利な機能です。 「持ち出し中」と表示された後は、配達員が荷物を持って移動している段階であり、通常であればその日のうちに配達される見込みがあります。
追跡画面では、「配達中」「配達完了」などのステータスが段階的に更新されるため、荷物の到着を効率的に予測することができます。
また、通知機能を設定しておくことで、ステータス変更時にメールやアプリ通知を受け取ることが可能です。
荷物の種類によっては、より詳細な動きが表示される場合もあり、安心感を得るためにも積極的に活用するとよいでしょう。
必要な手続きと管理方法
対応すべきケースと注意点
配達予定日になっても郵便物が届かない場合には、すぐに郵便局に連絡を取ることが重要です。
配達状況が追跡サービスで「持ち出し中」と表示されたまま長時間変わらない場合、配達に何らかのトラブルが発生している可能性があります。
このような場合、最寄りの配達担当郵便局に電話で問い合わせることで、現在の状況や見通しについて詳細な説明を受けることができます。
特に重要な書類やチケット、期限のある荷物などを待っている場合は、受取の遅れが大きな影響を与える可能性もあるため、迅速な対応が求められます。
また、過去に似たようなトラブルがあった場合は、配達員や郵便局側と事前に連携しておくことも有効な手段です。
万が一、配達ミスや紛失が発覚した場合には、調査依頼を出し、補償制度の対象となるかどうかも併せて確認すると安心です。
不在時の受け取り方法
外出が多く在宅が難しい場合には、荷物の受け取り方法を工夫することでスムーズな対応が可能になります。
たとえば、あらかじめ「郵便局留め」サービスを利用すれば、希望する郵便局に荷物を留め置きしてもらい、自分のタイミングで受け取りに行くことができます。
また、「コンビニ受取」サービスを利用することで、近隣のコンビニで24時間いつでも荷物を受け取れる便利さがあります。
これらのサービスは、事前に指定する場合や再配達の際に選択することができ、時間に制約のある人や多忙な方にとっては非常に便利です。
さらに、家族や代理人による受け取りが可能な場合もあり、本人確認書類を持参すれば対応できることがほとんどです。
このように不在時でも柔軟に対応できる手段を知っておくことで、配達トラブルや再配達の手間を軽減することができます。
まとめ
郵便が「持ち出し中」となった時点で、すでに配達は始まっています。
通常であればその日のうちに届くことがほとんどです。 到着時間の目安や確認方法を知っておくことで、安心して荷物を待つことができます。
何かトラブルが起きた場合でも、この記事で紹介した手順を参考に冷静に対処しましょう。