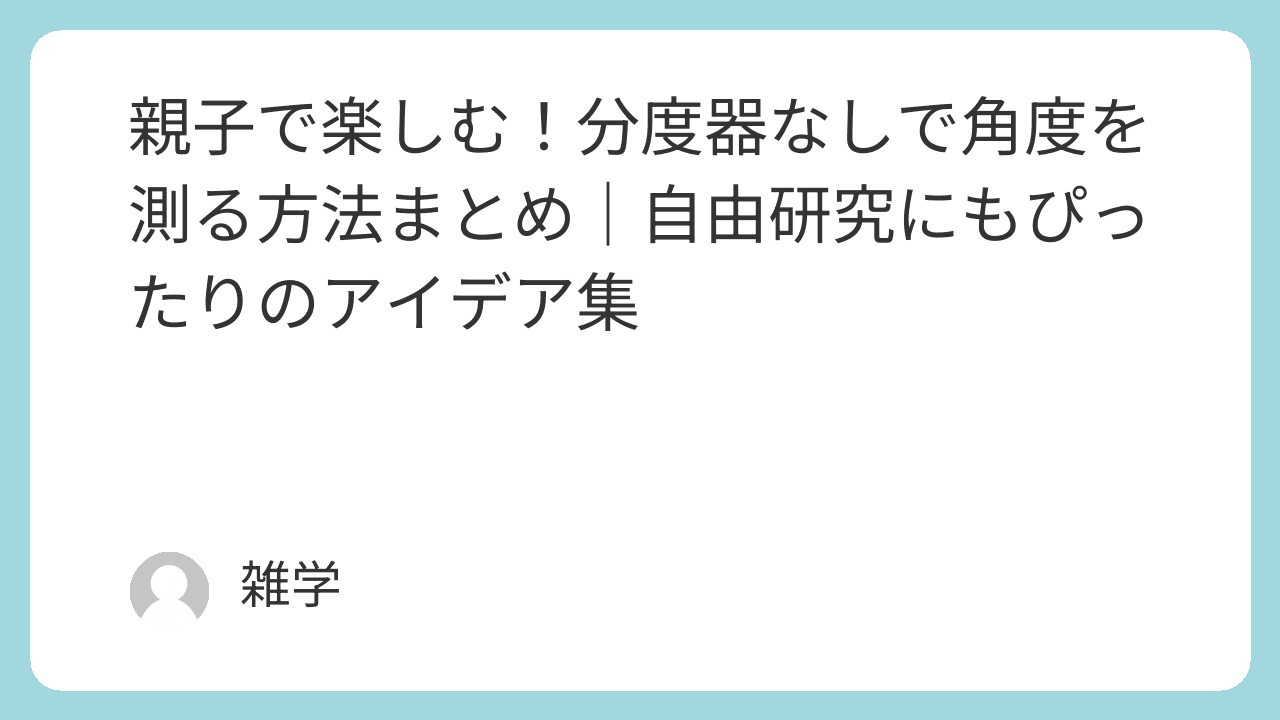分度器がないとき、角度ってどうやって測るの?と困ってしまうことはありませんか?
でも大丈夫!実は、家庭にある身近な道具や、ちょっとした工夫だけで角度を測る方法はたくさんあるんです。
この記事では、三角定規や折り紙、スマホアプリなどを使って、分度器がなくても角度を楽しく学べる方法をやさしく紹介しています。
とくに、小学生のお子さんと一緒に楽しめる内容をたっぷり詰め込んでいるので、自由研究や家庭学習にもぴったりです。
「算数はちょっと苦手……」という方でも安心できるように、わかりやすい言葉とやさしい進め方でまとめました。
角度の仕組みを身近に感じながら、親子で楽しく学ぶヒントを見つけてくださいね。
角度ってなに?はじめてでもわかる基本知識

角度とは、2本の線が交わったときにできる「ひらき具合」のことです。
このひらき具合を数値で表すために、「度(ど)」という単位が使われていて、角度は0度から360度まであります。
角度が0度に近いと線同士がほとんど重なっていて、180度に近づくほど開いていき、360度になると一周ぐるりと回った状態になります。
算数でよく出てくる角度には、「鋭角(えいかく)」「直角(ちょっかく)」「鈍角(どんかく)」という3つの代表的な種類があります。
鋭角は90度より小さい角度で、細くとがった感じの角度です。
直角はちょうど90度で、机の角やノートの端などによく見られます。
鈍角は90度より大きくて180度より小さい角度で、少し大きく開いた印象のある角度です。
身のまわりにも角度はたくさんあり、たとえばドアの開き方、ハサミの開き具合、扇子のひらきなど、いろいろなところで角度を見つけることができます。
ふだん何気なく見ている物の中にも角度のヒントがあるので、角度を意識しながら身近なものを観察してみると面白いですよ。
分度器がないときどうする?角度を測る基本の考え方
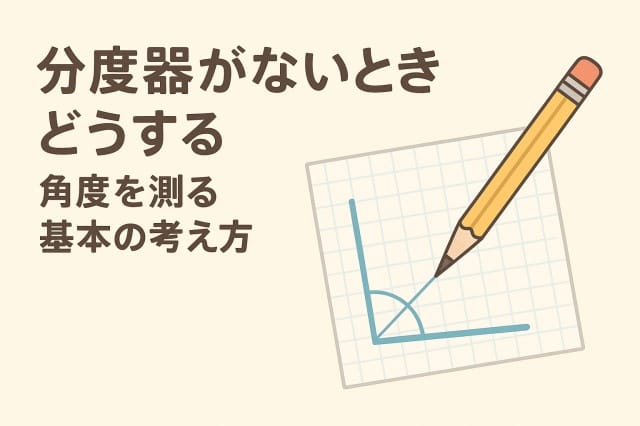
分度器がなくても、角度をある程度の目安で測ることはできます。
もちろん、ぴったり正確に測ることは難しいのですが、「おおよそこのくらいかな?」という感覚を養うことで、角度に対する理解を深めることができます。
ちょっとした工夫で、家庭にある道具や紙などを使って角度を知ることができます。
たとえば、ノートの角を使えば90度の直角が簡単に作れますし、折り紙を使って三角を作ることで、45度や60度などの角度も再現できます。
道具がないときこそ、身近なものを工夫して使ってみると、新しい発見があるかもしれません。
分度器がないときでも、角度に対する「感覚」や「想像力」を育てるよいチャンスになりますし、親子で一緒に試してみるのも楽しい学びになります。
家にある道具でできる!角度の測り方いろいろ
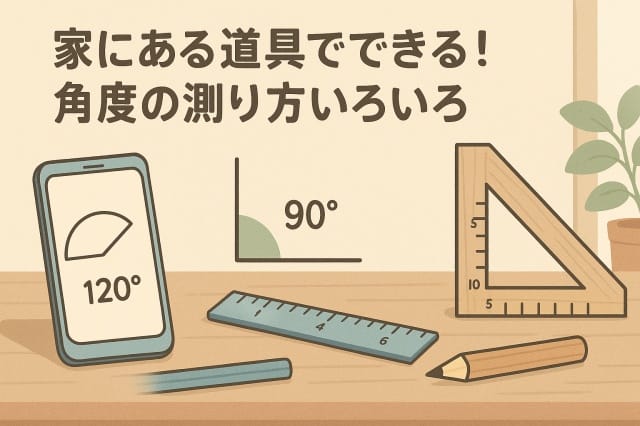
定規と三角定規を使ったシンプルな方法
三角定規には45度・90度・60度など決まった角度があるので、それを使えば簡単に角度を測ることができます。
紙の上に三角定規を当てて、角の形を写し取るだけで角度が確認できるので、算数が苦手な子どもでも安心です。
また、2枚の三角定規を組み合わせることで、30度や120度などさまざまな角度を作ることもできます。
透明な三角定規なら、下の図形が見やすく、正確に線を写せるのも嬉しいポイントです。
さらに、カラフルな三角定規を使うと、視覚的にも楽しく角度の学習ができます。
コンパスで円を描いて角度を導き出す
コンパスを使ってきれいな円を描くことで、その中心から放射状に線を引いて角度を作ることができます。
たとえば、円を6等分すると、それぞれの角度は60度になります。
12等分すれば30度、4等分なら90度といったように、分割の数によってさまざまな角度を生み出すことが可能です。
コンパスを使った方法は、図形の美しさを楽しみながら角度に親しめるので、自由研究にもぴったりです。
学校の授業より少し進んだ内容かもしれませんが、おうちで親子一緒に挑戦してみると楽しく学べますよ。
紙の折り目を使って角度を作るコツ
紙をまっすぐ半分に折ると90度、そのまた半分に折ると45度が簡単に作れます。
さらに工夫して3等分すれば、おおよそ60度の角度も作れます。
折り紙やチラシなどを使えば、身近な素材で楽しく角度を確認できますし、何度でも練習できるので安心です。
折った角度を線でなぞって見えるようにしたり、色ペンで塗ることで、視覚的にもわかりやすくなります。
また、紙の折り方によってできる角度の違いを比べてみるのも良い学びになります。
時計の針の角度をヒントにするテクニック
アナログ時計の針は、時刻によってさまざまな角度を作っています。
たとえば、3時と12時の間はちょうど90度、2時と12時なら60度、1時と12時では30度と、時間の変化によって角度が変わります。
この特徴を使えば、時計の文字盤を見ながらおおよその角度を知ることができます。
紙に時計の図を描いて、針を描き加えることで、自分だけの「角度時計」を作るのもおすすめです。
時間と角度を結びつけることで、日常生活の中に算数の楽しさを見つけられます。
スマホやタブレットを活用!おすすめアプリで角度を測ろう
子どもでも使える角度測定アプリランキング
スマホには無料で使える便利な角度測定アプリがたくさんあります。
たとえば、「Angle Meter」や「Smart Protractor」は、スマホの画面に表示される線に合わせて角度を測ることができるアプリです。
アプリを起動して、スマホを測りたい角度の面に合わせるだけで数値が表示されるので、操作もかんたんです。
なかには、カメラ機能と連動してリアルタイムに角度を測れるものもあり、親子で一緒に楽しく使えるのが魅力です。
アプリによっては、角度を記録できる機能や、測定結果を保存して自由研究に使えるものもあります。
子どもでも直感的に使えるデザインになっているので、家庭学習のツールとしてとてもおすすめです。
さらに、図形の勉強だけでなく、家具の角度調整やDIYにも応用できるため、大人と一緒に使うことで実生活でも活用できます。
スマホで角度を正しく測るためのポイント
スマホで角度を測るときは、画面を測定対象に対してしっかり水平または垂直に保つことが大切です。
スマホをまっすぐ当てる、ブレないように手を安定させる、机や壁に沿わせて固定するなど、少しの工夫で測定精度がグッとアップします。
アプリによっては、キャリブレーション(初期補正)機能があるので、最初に設定をきちんとしておくと、より正確な角度が測れます。
また、測定中は画面に表示される数字をしっかり確認して、わずかな変化にも気を配ることがポイントです。
静かな場所で集中して使うと、よりスムーズに測定できます。
写真を使って角度を調べる便利な方法
スマホで撮影した写真に線を引いて、角度を自動で計算してくれるアプリもあります。
たとえば、撮った写真に指でラインを描くだけで、その角度が数値として表示される便利な機能があります。
この方法なら、後からゆっくり確認できるので、外出先や学校などでも気軽に使えます。
写真を使った角度測定は、図形の学習だけでなく、建物や自然の中の角度観察にも応用でき、自由研究や観察レポートにもぴったりです。
お気に入りの風景や身近なものの角度を測って、写真と一緒に記録すると、楽しい学習アルバムができあがりますよ。
分度器がなくてもOK!親子でできる楽しい角度の測り方
紙とペンでできる!角度当てクイズにチャレンジ
いくつかの角度を紙に描いて、どれが何度か当てるゲームをしてみましょう。
たとえば、45度・60度・90度・120度など、代表的な角度をランダムに描いて、それを見た人が「この角度は何度かな?」と予想する遊びです。
子どもが友達と一緒にクイズ形式で取り組むと、ゲーム感覚で自然と角度の感覚が身につきます。
正解を出すにはどこを見ればよいのか、紙を折ったり、三角定規で合わせて確認したりと、いろいろな方法を試せるので、飽きずに楽しめます。
答え合わせは、三角定規やスマホアプリを使っても楽しいですし、正解したらシールを貼るなど、工夫すれば達成感もアップします。
算数×工作!自分だけの角度図鑑を作ってみよう
角度の例を切り取ってスクラップにしたり、オリジナルの角度を作ってノートにまとめてみると、算数がもっと楽しくなります。
「このページは鋭角特集」「次は直角コーナー」といったテーマごとにまとめてみるのもおすすめです。
雑誌やチラシから角度が見える部分を切り抜いて貼ったり、自分で描いた図形と角度を組み合わせて解説を書いたりすると、自由研究にもぴったりな資料になります。
図鑑の表紙をデザインして、タイトルをつけてみると、作品としての満足感も高まります。
学校の授業や自由研究に使える!角度遊びアイデア集
「この部屋の中で一番大きい角度を探そう!」など、身近なテーマでゲーム感覚で楽しめます。
たとえば、椅子の背もたれの角度や、ドアの開き具合、ひじの曲がる角度など、体や家具の中にある角度を探して記録するのもおすすめです。
角度を見つけたら、スマホで撮ってアルバムにまとめたり、どの角度が一番大きかったかをランキングにするのも面白いですね。
夏休みの自由研究として提出するなら、角度の測り方、使った道具、測定結果をまとめて、感想や気づいたことを添えると充実した内容になります。
親子で一緒に取り組めば、遊びながら学べる貴重な時間にもなりますよ。
覚えておくと便利!角度の代表値を測るコツ
45度・60度・90度を簡単に作る方法
折り紙や三角定規で簡単に出せる代表的な角度を覚えておくと便利です。
たとえば、紙を半分に折ることで90度の角度ができます。
そこからさらに半分に折ると45度になります。
三角定規を使えば、60度や30度なども正確に出せるので、道具があるとより便利です。
また、45度・60度・90度の角度は、工作やデザインでもよく使われるため、日常生活の中で活用できる場面も多くあります。
身近な紙や文房具でこれらの角度が再現できると、算数がぐっと身近に感じられますよ。
50度・55度など近い角度を出す工夫
ちょうどの角度がないときは、近い角度を組み合わせて出す方法もあります。
たとえば、60度の角度から少しだけ角度を狭めて、50度前後の角度を目安で作ることができます。
逆に、45度の角度に少し広げた折り方をすることで、55度に近い角度が得られることもあります。
このように、「おおよそ」の感覚で近似していくことも、算数の大事な考え方のひとつです。
また、実際に紙を何枚も折って比較してみると、視覚的な違いもはっきりしてきて、楽しく学べます。
よく使う角度の「目安表」を作っておこう
自分で作った角度早見表を手元に置いておくと、いざというときにすぐ役立ちます。
45度・60度・90度・120度・135度など、よく使う角度を一覧にしてノートや画用紙にまとめておくと便利です。
紙を折って作った角度を貼って見本にしたり、角度ごとに色分けして見やすくすると、より理解が深まります。
自分だけの「角度辞典」として、学習のたびに見返すことができるので、親子で一緒に作ってみるのも楽しいですよ。
分度器なしで測るときの注意点と限界
正確さとおおよその目安の違い
分度器を使わない方法は「だいたいの角度」を知るのにはとても便利です。
特に、家庭学習や自由研究などでは、正確な数値よりも「どのくらいの開きか」という感覚をつかむことの方が大切な場面も多いでしょう。
ですが、たとえば製図や理科の実験など、1度単位の正確さが求められる場面では、やはり専用の分度器や測定機器が必要になります。
目分量では限界があるため、「どの場面でどこまでの精度が必要か」を見極めて使い分けることが大切です。
測り方によって誤差が出ることもある?
角度の測定方法によって、思った以上に誤差が出ることがあります。
たとえば、紙がゆがんでいたり、線を引くときに手がぶれてしまったり、スマホを斜めに当ててしまったりすると、結果にずれが生じます。
また、アプリを使う場合でも、スマホのセンサーの性能や、使用する場所の明るさによっても、わずかな誤差が生じることがあります。
こうした誤差をできるだけ減らすためには、紙をきれいに折る、しっかり定規を当てる、スマホを安定した場所に置くなどのちょっとした工夫がとても効果的です。
何度か繰り返して測定してみることで、平均的な角度を導き出すこともできますよ。
テストや提出課題で使っても大丈夫?
提出課題では、正確さが求められることが多いため、分度器がある場合はできるだけ使用するのが安心です。
とはいえ、どうしても分度器が使えない状況であれば、工夫して測ったこと、そしてその方法を丁寧に説明することで、学びの姿勢が伝わります。
自由研究や観察レポートでは、「近似的に角度を求めた」ことも立派な工夫として評価される場合があります。
また、迷ったときには学校の先生に相談して、提出に適した方法かどうかを確認するのがもっとも確実です。
自信をもって提出するためにも、わからないことは積極的に聞いてみましょう。
よくある質問Q&A|分度器なしで角度を測るときの疑問
正確じゃなくても自由研究には使える?
自由研究では、楽しみながら角度を体験することが大切なので、多少の誤差はOKです。
正確な数値よりも「角度の考え方」や「測る工夫」を知ることのほうが、学びとしてはとても価値があります。
「どのようにして角度を測ったのか」「どんなことに気づいたか」「どこが難しかったか」といった観察や振り返りをしっかり書いておくと、より深い自由研究になります。
たとえ角度の答えが少しずれていても、自分で考えて行動したというプロセスが評価されることも多いので、安心して取り組んでくださいね。
どんな道具を使うのが一番かんたん?
三角定規や紙の折り目は初心者にとってとても使いやすく、誰でもすぐに試せるおすすめの方法です。
三角定規は学校の筆箱にも入っていることが多く、45度や90度といった基本の角度を簡単に確認できます。
紙の折り目は、道具がないときにも活躍してくれるアイデアで、正確さには限界があるものの、感覚的に角度をとらえるにはぴったりです。
また、道具に慣れてきたら、定規やコンパス、スマホの角度アプリなどに挑戦してみるのも楽しいですよ。
小学生でもひとりでできる測り方は?
紙を折って作る方法や、三角定規を使う方法なら、小学生でも楽しく挑戦できます。
とくに紙を使った角度の作成は、ハサミやのりを使わずにできるので安全で安心です。
紙を半分に折るだけで90度、そのまた半分で45度ができるため、工作感覚で角度の学びに触れることができます。
三角定規を使って図形をなぞってみたり、ノートに角度の一覧をまとめたりするのも、自分のペースでできる楽しい学習法です。
時間をかけて繰り返すことで、角度のイメージも自然と身につきますよ。
まとめ|分度器がなくても角度は測れる!工夫とアイデアで算数がもっと楽しくなる
分度器がなくても、角度を測る方法はたくさんあります。
家庭にある道具やスマホアプリ、紙の折り方など、工夫しだいで親子一緒に学びを楽しめます。
夏休みの自由研究や、ちょっとした家庭学習に、ぜひ試してみてくださいね。